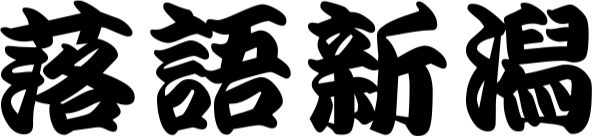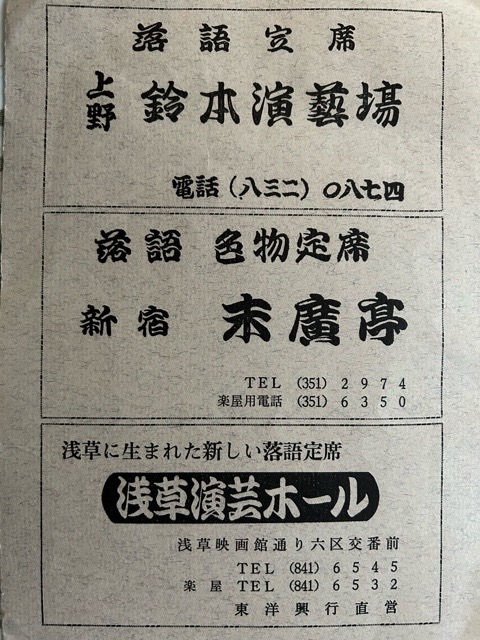�S�֓���w���ꌤ����A���@���ꂪ����Ȃ��Ƃǂ����ɓ��̐e�r�c�̂ƌ����������q�����g�D�@���S�ƂȂ����͓̂��嗎���@���a�Q�O�N��㔼�@�����̎傾������w�����ɌĂъ|���@�c�������͓�����@����ƈӌ�������Ȃ�������ł��傤���˂��`
�������̍ݐЊ��ԁi�P�X�U�T�`�U�X�j�ő���ɏo�Ȃ����͉̂䂪��w���܂߂P�O�Z���x�@�����Z�͖@���@���̑���őn�����̓��嗎�������o�[�łȂ��������Ɏ��܂��Ă������ɍu���肤�@�����̋�J�b���@�܂��l�Ă�łƌ�����莩��Ă��́u�S���A�v�@�S�����S�w�A�Ǝ��߂��Ƃ��đS�w�A���牣�荞�݂��|����ꂽ�@�u�ӂ�����ȁI�v�u���������ɂ���v�u���̂�ς���I�v�V�����̉���Ȃ��A���Ȃ�ł��˂��`�@�ܘ_�A���Ƃ��Ă͏d�X���m�̏��̊m�M�Ɓ@���̂�ύX����܂ŕ����ɋ�������@���Ђ̋������|���@������ƌ����āu�͂������ł����v�Ƃ̓C�J�̃L���^�`�i������ɂ܂�t���Ȃ��ʼn������j�@�u�A���Ƃ��ē���ꑶ�ł́i�ꉞ�l���Ă�t���j����v���܂��v���������肤
�@�e�Z�ɒ������قǂ̂��Ƃ͂Ȃ��Ɠ��嗎���@���̒��x�̒m�b�͎������킹�Ă����@�����I�ǂݕ����p��Ɂ@�S�֓��E�E�E�̑S���I�[���Ɠǂ܂��邱�ƂőS�w�A�֒��d�Ȃ�ɏo�����@����Ƃ͂��̂���
���݂ɂ������̌�������̑S�w�A�i��X�،n�j�̈ψ����͉䂪��w�́@�S�w�W��ŃX�[�c�Ƀl�N�^�C�p�œo�d�@�u�w���̃N�Z���Ă��̃i���i���p�j�͉����I�v�u�w�������ė����I�v�����W�������̂ł����@��ȃ����[�ł����˂��`�@���̓��勳�������A�ꂵ�����吶�B�@�����A�C�r�[���b�N��w�Ƀ��[�h���ꂽ�a�J�W�t�@�b�V�����Ȃ̂Ɋw�����𒅍���ł����@�ǂ�����Ƃ��Ȃ��������������炴��߂����畷�����鐺�Łu����Ȃɂ����傤�̃o�b�`���Ђ��炩�������̂��I�v�u���镨�����Ă˂��̂��v�u�n�R�l�I�v�C�W���ł�����˂��݂��i�Ёj���݂ł��@���肽���Ă�����Ă��炦�Ȃ������A���̍��݂��Ă����Ă����@���傪�Ȃ@�������������@�������͌����Ă܂���@�ōu���̂��Ƃ̑���@�A���̓S�̝|�̌���@�P�V�엎��͉���Ȃ��Q�������͉���Ȃ��R�o�O����ɍs���Ă��������ĕ�V�͎��Ȃ��@�w���Ƃ��Ă̖{�������o���邱�Ɓ@����̋c��͂��̊m�F�̂݁@����ȊO�͂Ȃ��@�P�ƂQ�͂�낵����ł����R�ƂȂ�Ƃ˂��`�@�e�Z���ɉ��ƌ��𑵂��u�|�͔j�邽�߂ɂ���v�u���ǂ��˂��`�v�u����ȂƂ�����́H�v�䂪�����͂Ɖ]���ƌ`����̎ӎ��̃Z�����j�[�̂��Ɓu����ɍs�����I����ɁH�v���������t�ɂ��̋��ŊF�ŗ[�H�̒����ւ�������ł����@�ő���ɖ߂�܂����F����C�͂�����ł����@�e������u�������`�v�ǂ����ŕ������悤�ȁE�E�E�X�g���b�v�����̋q�Ȃ��狓���鐺���Ɓ@�`�����������̍Ō�͑S���ő�̊y���݂ɂ��Ă���u�o����v�܂荇���R���p�@�@����������Ē����̐_�y��@��O����̑�L�ԂŖ��������Ă̂P�O���Z�@���吶�B�͂��܂���ł����Ȃ����u�ǂ�Ȃ��Ƃ���́H�v�@�I���W�i���x�̍���u�Ȃɂ���I�v�x�̂̃��x�����n���p�łȂ��e�Z�������I�u����Ȃ��Ƃ��ĉ��ɂȂ�́H�v�������́I�u���ꂪ�ǂ��������Ă����́H�v�w���̂˂��`�l�i�V�g�j���C���ǂ��b���Ă���Ƃ��ɂ���E�E�E�x
�@�����܂��@����ł͌��ʂ\���܂���R�ʃ��Z�_�̃N���X�}�X���߂Â������`�Ŏn�܂�W���O���x���Q�ʊw�K�@�̗L�y���ʼn�܂��傤�@�ȊO�Ɩ��킢�[���̎��ł��@�P�ʉ䂪�����́E�E�E���̂Ɖ̎��́H�@�]��ɂ��V�h�i���j���Ĕ��\�͂ł��܂���@�w���̂�邱�Ƃł�����@���߂�����˂����@����̃I���W�i���x�̋����ĉ������@�������u�O�@��t�ɒ����n�ɂ���Ă��܂������[���w�ǂ�����������̐l�Ԃɖ߂��ĉ������x�Ɨ��݂��݂��Ȃ�����Ɓw�����I���������͂��̂܂܂Ɂx
���ł��e��w�����n�a�A����]�����Ă���
�@�̈��n��茵�����u�P�N�Ⴆ�Β��P�����R�v�̐��E�@�P�N�W�����Q�N�z��R�N�V�c�S�N�_�l�̒c��̐���@�������n����ł������܂��@�������́u���v���u�ʁv�Ƒւ��Ă͂Ȃ�ʁ@�n����́u����v���u���v�Ƃ�������h�Ƃ́@�ÓT��������ʔ����I�����b�g�[�ɂ��ā@�g�[�V���[�ł͂���܂���̂ŃA�S�������t���ďj�V�́H�~
�A����́@090-4911-5544
�w�����v���܂��@�̘Z��ډ~�y�i�w�����j�����S�҂Ɂu���F�������̐l���狳����Ă͂����܂����v����ȕ�����̎w���͂��~���Ȃ����@�i�K�I�Ɋm�����ꂽ�w���@���}�j���A�������Ă܂��@�ʔ�����Nj��������ˍ�Ƃ�����Ă܂�
�������̂Q�@�щƖ؋v��t���̐�㐳���t�Ɂu�t���@�ǂ����Ė݂��ăJ�r���������ł����ˁH�v�u�o�@�E�J�E���E��E���E�͂���E���E���˂��`���@�炾�I�v�@�m�g�j�g���ő�g���ƌ����܂�������Ȃ��Ƃ͂���܂���@��ȂŃg���i���j�ƌ����͍̂ŏI���҂��w���܂��@���̓��̖،ˑK��Ȓ��R���c����u���v�Ɖ]���Ƃ��납�痈�܂����@�O����ڐ^�ł����̑��̉��҂ɉ����Ɂ@�����Ɏ��ɕ��Ŕz����������g���i���j�ƌĂт܂��@���̑O�O��T��i���������j��������̔ԑg�ł����b��ɂ��Ă܂������E�E�E�@���ꂾ���͌��������@�a�H�i�m�H�ł��j�Ŏ�M�����Ă͂����܂���@����Ȃ���@�͂���܂���@����i�Ȏd�����Ǝv���Ă���̂ł��傤���H���炿���@������ɂ��ڂꂽ�H�ו���`��ׂ�̐l�̈ߕ��ɂȂ������̂ł����@�M��o�͎�Ɏ����܂��@�m�H�ł̓e�[�u���ɋ������������ڂ��Ȃ��悤�ɂ��ā@���̂��ƃR�[�V�[�ł�����Ł@���́u�S�z�O���ꌤ����A���v���t�@�z�R��Ƃ͈Ⴂ�܂��@���̂Ƃ������̓����@��ӌ�����܂����Ȃ�E�E�E
�w���x�i�����Ɍf�ځj
�l�ԃo�J�ɂȂ�Ƃ��Ƀo�J�ɐ���Ȃ��قǃo�J�ł͂Ȃ�
�w�����\�P�x
��@�i�����Ńm�~�オ����肷��z�ցj
�����܂ł��ď��������̂��˂��`�@�p�Ă����̂��E�E�E�@�₾�₾�@���肽���Ȃ��˂��`
��@�o���͊w���ł͂Ȃ��I�@�Љ�ɏo�Ă��炪�����I
�@�i���̌�@�Ƃ����ɗ��@��ɗ����ā@��ꗎ��҂Ȃ�@�Ȃ�m��@�x���I�@�h�p�l�P�W�O�扽���֍s�����`�@�����ɋ����j
�O�@�����̎�͖����ŕԂ��I�@�̂ŕ������Ƃ͑��Ȃ�ʁI�@�N�����]���ʌ́@���q�����ɑ��Ă�����]���y�����邪�E�E�E
�l�@���q�����Ƃ̖������ւ���@������傫���J������@�X�J�[�g��������グ�K�����q�͐F�d�|���ł���@�����邱�ƕK���@���̑̂ŕ������Ƃ͍\��ʁ@���E�E�E�E�E�E
�܁@�R���p�ʼnA������肳��ʂ悤�����₫���ŏ��q�����ɑ��u�E���I�v�Ɖ]���Ă͂Ȃ�ʁI
�@�����ɓ������Ă��鏗�q�͌��x��m��ʌ�
�Z�@�����͊w���̐������܂�Ɩ����m���@�ǂ��̃T�[�N�����������ɂ���Ȃ��������ڂ�̊��������W�c�Ǝ��o���ׂ�
���@�Љ�ɏo�Ă��̈�|�������ă^�C�R�����ɂȂ�@��������ۂނ��Ƃ����Ă̂ق��I
���ꉃ��ɓ�����ւ�
���@�G���f��قɓ��ꂵ���҂��Ăяo���ہ@�����̏Z���@�o�g�Z�@�����ł��邱�Ƃ�������
��@���̑䎌���o���邱�Ɓ@�������|�@�u���x�@�ɂ��ɂ������̂�����@�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܁`���@�Ȃ��`���q�l�ɂ���f���\���グ�܁`���@���̋̂��B�����ɂ��@�x�薺�̈ߑ����͔��ɂ͌������Č������ĐG��ʂ悤�@�����тɁ`�ʐ^�B�e�Ȃǂ͐�ɐ�Ɉׂ���ʂ悤�[���肢�\���グ�܁`���@�w�������`�x�i�i��҂ɂ݂��Ԃ����j
����ł͂��p�ӂł��܂����ł��傤���H�����Y�b�N�X���^�D�[�g�v�^���^�J�^�b�^�\�^�J�^�b�^�[
�@����x�q�̒ǂ����������@�t�@�[�̃R�[�g���͂��������̖��Ɗ���̉��@����̂��łŌ��������E�E�E�G�ɂȂ�܂����@���̌����̏��E���i�l��s���E��Ɂj�ƂȂ�Ɩ��W�Ɂ@�X�|�b�g���C�g����_�i�H�j�u�W���������ׁw�M����˂��`�I�x�Ɠ{���E�E�E�i��߂閘�ɏo���E���i���Q�Ɂ@�����܂ł͐��̒��w���ł͂Ȃ����́E�E�E��������ł����˂��`�@���l����ƓV�E�������̂����E�E�E�@�D���������m�̏��Ȃ�@��������Ȃ��˂��`
�@�����f�{���������̂ł�
����ꌵ�������삩�甪���q�`�Y���ɔ�т����đ�{�ւƓ]�X�Ƃ���@�l��s���ׂ̈Ƃ��ɂ̓i�C�X�o�f�B�[�̕l�����܂ŏo���肤�@���Y�������Ȃ��Ă˂��`�@�͖��R�̂ɂ��킢�ł��Ȃ�����͂���œ˂������Ă��邾���ŏ��X�����ĈȊO�ƍD�]�ł��ā@�h�T�����Z�������ω��������肪�����@�������w���^���ɔ�ׁ@�S�̎l�V�ƑΓ��H�@�݂���F�Ɍ����������ɏƂ炳��W�������~���̏�
�@�~�߂Ă����ȗx�薺��@�w���Ɋ���ꂳ���@�s���˂Ȃ�ʂ��̑厖
�@��`���������Ȃ��i�m���|���E�m���Z�N�g�j�@�Ί�Ō}���Ă��ꂽ����̊F����@�����Ȃ�������������Ă����x�薺��@�L��E�E�E
�@����҂̉䂪�ЌP
��@�ア�l�Ԃقǐl�̏�ɗ���������
��@�瑊���ςā@����̐S���������I
�O�@���i��݁j�Ɋ�@���������Ƃ��̏u�Ԃ̔��f�͂�{���I�@���̐��ɂ��`����
�l�@�������Ȃ�Ύ��R�Ɋw�ׁ@�����i�����̏������܂߁j�͗��j�Ɋw�ׁ@����͐فi�n����j�Ɋw��
�܁@�w���̂��͂�x��m��߂���قǂɒm��@����Ȃ����āw�l�͂�������Ȃ���܂��x�@�l�Ԑ���b����
�@�������ӂ��@���w����n�i�Ɋ|��
�@���Ƃł��������
�@�o�c�҂ɂƂ��Ă����̘b
�@�P�X�W�T�N�K�V������̈�Ԕԓ��ł����������d�H�̖��_��O�H�������ɉ���Ċ��������b��
�@�K�V������̐l�����q�ׂ�ꂽ���Ɓ@���a�R�O�N�����̒�����Ǝ��O�ɂ��ču���̍ہw��Ќo�c�Ɍ������Ȃ����̂̂P���������Z�ł��@��N�Ɉ�x�̌��Z�ł͉�Ђ̏��c���ł��Ȃ��@�F������������Z�����Ȃ����x���̂Ƃ���l�̒�����Ǝ傪�w�K�V���͂�̂悤�ȗ��h�Ȋ�Ƃ͂��ꂪ�ł��܂����ǁ@���e��̂悤�ȏ����ȉ�Ђł͖����ł���x����ƍK�V������C�X����X�b�N�Ɨ����オ�艉�d�֍s���ꌾ�w���C�ł�ȁI�x�ƌ����Ĕw�������Ė߂�@���̂Ƃ��̎�u�҂�����@�K�V�������q�˂Ă��āw���̂Ƃ�����ꂽ�i�i�����j�j�𒉎��Ɏ��s���ă}�A�}�A�̉�ЂɂȂ�܂����x�Ɨ���q�ׂ��@���̐l�͓|�Y������Ђ́����Ј����n������Ɓ@���s�Z���~�b�N�̑�\��a�v����ł���
�^�������}�i�[
�H�̂���@�@�s�u�̐H���|�ȂǂŁ@�p����R���b�P�Ȃǂ�����ł�����Ɓ@�H�אՂ��b���^�Ɏc����܂��@����Ă͂����܂���@�H�אՂs���ɂȂ�悤�ɎO���ł�����̂ł��@�S���ĉ������@���i�ǂ�
���̂Q�@�H�����͉�b�����Ȃ���y�����E�E�E���̒��ɐH�ו���������ƕs���ł��@�L�`���ƈ��ݍ����Ƃ���@���{�̐H�̂���@�ِ͖H�ł����@���Ɏ��̉Ƃ̂悤�Ɂ@�Á`�����������@�E�`�������ł���
���̂R�@�̂�فE�E�E�������т��������̂ł́i�����H�j����܂���ƌ����Ĉ炿�܂����@���_�͏��m�ŁE�E�E
���̂S�@�����Ȃ���H�ׂ�����肵�Ă͂����܂���@���ƂɋA���Ă���L�`���ƍ����Ă��疡����ĐH�ׂĉ�����
���̂T�@���O�Ŗ������Ă��炢�������H�ו���̎�ɏ悹�悤�Ƃ��܂��@���M�Ȃǂɏ悹�ĉ������@�f��̏�ɐH�ו���u���Ă͂����܂���
���̂U�@�]�˂��q�����܂�̍ۂɁu�A�[��������Ղ�ƐZ���āi�����j�ăF�`�v�]�˂��q�̐����������Z���܂��\��������̏����ł�
���l�Ȃ��Ƃ��@�s�u�ł��閟�ˎt���u�\�o�ɂ�������Ղ�ƐZ������@�E�`�̕~�����ׂ����Ȃ��I�v�Ƃ��������Ă����ƁE�E�E���ʂ��˂��`�@����Ȃ�w���������ʓǖ{�x����`�����ǂ݉�����I�@����ȓ`�������ԈႢ�ł��鎖�@�@�u�ł�䥂łĂ���I�v�u���̏�v�ȕ�������������悤�ŁE�E�E�v�L���ȘV�܂̃\�o���̂���l��������Ă܂����@���̂܂݂ɂ�Ȃ��ł��̂܂ܐH���܂��@���̒����u�₩�ɂȂ肢����ł��E�E�E �\�o�������鎞�������Ă���Y�Y�[�Y�Y�[�Ɖ��𗧂Ĕ����g�킸�z�����ޔy�����ʂ̋��Ƃł��H�@���i�ɂ܂�Ȃ��@���[�����ł����𗧂ĂĐH�����̂ł͂���܂���@���𗧂Ă��̂̓��W�I����̗��ꂪ�n�܂�ł����@������ł����
�Љ�̃}�i�[�@�^�Ƃ͏K���ł��E���܂���ł�
�P�@�l�̑O�C�Œʂ�l�����܂��E�l�O��ʂ�Ƃ��͉�߂����ā@���͎蓁����Ă��������Ȃ����Ă�����Ȃ����`�E�E�E��
�Q�@�s�u�̃^�����g���l���Ȃ��Ől���w�����Ă��܂��@�l�Ɏw�������Ă͂����܂���@�e�����^���ĂȂ������̂ł����ˁ@���l�ɐH���̂Ƃ��@�H��ɕI�����Ĕ��ł����ču�߂�����l�@����Ă͂����Ȃ��d���ł��@����̒j�D�̕��@�����đ�����Ɏ�̍b�������Ȃ���U�蕥�炤�d���̐l�E�������܂����@��������Ƃ��E��̕��ɂ�����悹��@�������̎��M���Ă͂Ȃ�܂���@�H���ŁH�@���̎�͐܂����
�R�@���ł����ĐH����ړ�������l�@�Ȃ�������܂���
�S�@���l���畨��������Ă��@���Ԃ����Ȃ��l���E�E�E�@������w�m�`�Ԃ��x�ƌ����܂��ā@���̂悤�Ȑl�͏I���ɂ͒N���������ɂ���Ȃ��Ȃ�܂�
�@������e�̋������ׂ���ĂȂ��̂ł��ˁ@���̒���n��ׂ̑ΐl�Œ�����[���ł�
�T�@���l�̉Ƃ�K�˂�Ƃ��@�Ⴆ�e�q�ł����Ă���y�Y�������Ă������Ƃ͏펯�ł��@���A�q���������b�ɂȂ����Ȃ�@��������̕������̐e�ɑ����Ă�����͓̂��R�̂��Ɓ@������m�`�Ԃ��ł��@�������ꂽ���͒������Ȃ璼���Ɍ��̈����@���̂��Ɖ���Ȃ��l���@�E�E�E���Ƒ������Ƃ��I
�T�[�N���̌�y�@���Ǝ��ɏ���ɉ��������Ă��ā@�������낤�����ߍ��ށ@���̐e����͈�Ђ̗����Ȃ��@�e�̊�����Ă݂����@���̒��x�̉ƒ�Ȃ̂��Ɓ@�����ē��y��g���v�w�ŗ��Ă��y���ɂȂ�Ȃ��猾�t�͂��납���̈�Ђ��Ȃ��@�U�O�˂̑�l�Ȃ̂ł����ˁ@�]���̈炿�Ȃ̂ł��ˁ@�������E�E�E
�T�|�P�@���̋t�̃P�[�X
�w������̗F�l�@����݂��Ă��@�Љ�l�ƂȂ��Ă��̂܂܂Ɂ@����T�S�N�Ԃ�Ɏ��ƂɖK�˂Ă��ēd�b�ԍ����ēd�b���Ă����@�؋���Ԃ��Ȃ��Ǝ��ʂɎ��˂Ȃ��E�E�E�킴�킴�_�˂���K�˂Ă����@��������ʼn���ƂɁ@�������炻�̑O�ɕԂ��I�@�Ԃ������}�V�����ǁE�E�E
�U�@����g��ŐH������l�@��������Ε�����Ȃ��̂ł����H
�V�@��������Ƃ�������̎�̎w�ŎM�̏�̍����������l�@����g���@�H�ו��ɂ͔��ȊO�G��Ă͂Ȃ�܂���@�����ȊO��
�W�@�t�ɔ������肾���������ĐH�ׂ�@��������̎�͕G�̏�Ɏ�̕�����Ɍ�������i���@�Ў�E���ł��@�c�ɂ̂��N��Ɍ����܂��@�[�Ō��Ă���ƌ��ꂵ���d���E�w���ۂ܂���
�X�@�ƒ�ł̘a�H�@��l���߂��߂��̂��M�ɐ����ĉ������@�o�C�L���O�⒆�ł͂Ȃ��̂ł߂�ǂ��ł��E�q���ׂ̈ɂ��K���Â��ĉ�����
�P�O�@��ԑ�Ȃ��Ɓ@���͂�͈ꗱ�c�����H�ׂ邱�Ɓ@���Ă��ꂽ�l�Ɋ��ӂ����{���̊�{�ł��@����̊�{���̊�{�@�P�O�O�ȏ�́��̐����͂���܂���@���w��m��Ȃ��l�ł�
�P�P�@���o�y�j�ŁE�������ɎQ�����E�����O�w�A�[�̓}�i�[�ᔽ�H�V�w���ڗ����ẮE�E�E�����Ȃ��ł��傤�@�����H���Ŕ��������Ă�������̎�Ŕ��̖т���������E����͂����܂���@�Ў�@���Ƀf�p�[�g�Ŕ����Ă����z�e���̂��ٓ��Ńv�`�g�}�g�ɗ̃w�^��t�����܂܁@�ԂƗ̂���ǂ��ǂ��Ƃ��ăp�[�g����ɔC������m�b�@�O�Ȃ炵�܂���@�w�^����鎞�E���̂ق��Ɏ���g��Ȃ��Ă͂����܂��w�^�ɐH���ŋۂ��t�����Ă��邩��ł��E������z�e��
�P�Q�@�`�����������Ń`�����`�����Ƃ����������������@����Ȃ�ԓ��ցE�����𑖂点�Ȃ���炷�Ƃ́@�Ȃ炸�ҁI������E���@�ҁE�n�i�܂ݎ҂߁I�@��҂����łȂ��W�W�B�E�o�o�@������
�P�R�@�悭�u������Љ�ɂ�������܂����w�Ȃ�̂���ׂ��x�Ɛ\���܂��v�J�œx�X��������^��ł��@�F�l�s�v�V�Ɏv���܂��H�@�i��̕����Љ�E�܂葼�ҏЉ�ĉ��������̂ɂ킴�킴���ȏЉ���d�˂Ă���@�o�J���������ɂ߂��@�i��̏Љ�҂ɑ��Ĕ��Ɏ���ł��@�ǂ����̂ւ��ۂ������������O���o���Ă��炨���ƕK���ɂȂ��ā@������ւ��ۂ��������ł��Ȃ���ʂ̐l�܂ł��E�E�E�o�s�`�̉�E�ǂ����̈̂�����Ȃǂ��l���Ȃ��Ń}�l���Ă���E�E�E��[�����l���Ȃ����Ă�����Ȃ����ˁE�o�J�ɂ���܂���@�����ȉ����܂��@�����Ŗ���o�Ȃ������Ƀ^�}�ɏo�Ă��ăP�`������l�@���������͏�ɏo�Ȃ����l���L������̂ł��@�펯�ł�
�P�S�@�u�ǐ^�v���i�Ȍ��t�Ō����ł��@���Ȃ��Ƃ������ł͌����܂���@������]���Ȃ�u�^��^�v�ƌ����܂��@�����炱�̌��t��N���g���n�߂��̂��H�@��̂̃��[�c�͔��X�Ɓ@���̃X�|�[�c�E�̐l�B�����̒n���̂��̂܂��K���̗ǂ��Ȃ��n��̕����������ꂽ
�P�T�@�ߔN�l�N�^�C�̌��іڂɂ����ڂ������Ē��߂Ă܂��@�̂͂����ڂ��ł���ƃL���C�ɂȂ炵�����̂ł��E���ꂵ���I�Ɓ@���{�݂̂Ȃ炸�E�E�E
�̎҂̂������ɂ͔[�����E����ƃJ���[�̂x�V���c�Ƀl�N�^�C��
�P�U�@�x�X�g�̍Ō�̃{�^���͊O�����̂ł�
�V�����ł���Ƃ݂��Ƃ�����܂���E�㒅�̑��{�^���͗����Ă���Ƃ�������Ă���Ƃ��͊|���@�����Ă���Ƃ��͊O���܂��@�}�i�[���̃}�i�[
�P�V�@�r�W�l�X�X�[�c�ɔ���Ԃ̂����͂˂��`�E���Z���H
�P�W�@�V��������Ă����̃X�[�c�͍D���ł��@�V���͖��̓����ł����E�����������@�C�̓R�[�h�o���E���Ղ����ǂ��̐F�ƋP�₫�����Ƃ��]���Ȃ��ā@�r���v�͐̂���畆�A�����M�[�ł������ƂȂ��@�l�b�N���X�Ƃ��w�ւ̌��蕨�͐̂₭�����́i�l���ɓ���Ȃ����ƁE�|�l�E�̕�����҂Ȃǂ̗���̐l�B�j���g�ɂ��Ă����@�����̎������ł���Ɓ@���������т̌��іڂ�[�ɐ����āE�����ܗ��������ƋC������₭�����̂ł���
�P�X�@�ސE���ăT���f�[�����̐g�ƂȂ����j���@�����o�����h���Ȃ��E����Č������������E�������Ȃ��@���h�����߂Ĉ�Ԏ���Ƃ葁���g�߂ɂ�����́@���������̖����E�����ɔ��荞�ށE�߂����ɉ��������Ƃ̂Ȃ������y�R�y�R�ƁE���̍b�゠���Ė����ɁE�悤�₭���h������E����ő��l�Ɍւ��@�ǂ��܂ł��������̂��݂������E�]�����Ă��炢�����E���肽���������l�ԁ@�����܂ł��Ă�邩�˂��`�E�₾�₾�E�^�������Ȃ��˂��`
�Q�O�@�O���̍��œǂ�ŗ~�����{���E�E�E�ԈႦ�܂����@���̖{�̒��Ɂu���𗧂ĂĐ����悭������ׂ��v�ʂԂ��Đ������Ă�����ƌ�楂ɂȂ�܂��E���ɔN���́E�����ĉ��i�ł��@�u�˂͂�ɎO���̈�قǂ���ׂ��v�w�������ӂ����w���@�ɂ����x�@���̖{�ɍڂ���ꂽ����������͑S�ē��ށE����̋�������Ă���悤�ł�
�@��\���ĎO��V�܂Ŕ�r����Ɓ@���Ε��̔z������n�܂�E�˂̑����ׂ��E�����ɐH�ׂĂ��炤�̂��E�o�O��O��Ƃ���̂��E���̈א��̐��ɂ���̂����E��̔Z�������E���m���Ɋ����z�����o�`�ɂȂ��Ă����@���̂��Ɩ˂ɂ����Ղ�ƃU�u���Ƃ�����Ă��ǂ��̂ł��@�]�˕��o�`�̓`���̔Z���䂪�����@�Ȃ������E�����̊Â����邢�����E���̂̓�������@�����ł����{���E���R�ƂȂ�E�E�E���̂ꂥ�`�I
�@�����ˎm�E�͈�p�V���@����J��k�̈⍦���������������������@���̎��̊��R�̑�\�Ҋ⑺����Y�E�y���̓c�Ɏҁ@�����R���ˋ��̉|�����U�����Ă���̂ɋC�t����
�@����J�̎���ő��̖��ɋ��d�������Ē����V���@�����֓������R�̎R���L���@�D��炶�̂܂オ��u�o�J�ҁI�v�Ɠ{������V���R��グ���@���R���ł��]������Ȃ������⑺�Ə���J��k�����Ƃ͌p�V���͂悭�悭�^�����������̂��@���s����̌p�V���̏����W�����͊��R���e�˂̎傾�������B�̕]���͍��������@���̂悤�Ȋ⑺�Ə���J�ɑ�\�Ƃ��Ĕh���������R�̐ӔC�҂͒N���I�@�܂������j�Ɏc��l���ł́H
�@���̊⑺�ɑ��Ă�����Ԃ��ď���J�̎���Ղɂ����p�V���@���[���Z�Z�E�E�E��E�݂���v�ȕ��Ƃ͂Ȃ��Ă��ʂ���Ȃ�
�@���ꂩ�琼���ȉ��̊��R�E�C����V���̋��t���̏�����ɏ㗤�E��ÂւƁ@�V�I�g�ɑ��鑞���݂��Ăԁ@����ɂ��Ă����R���̍s�ׁ@���̂ƂȂ�����Ôˎm�̍ȁE���ɑ��Ă��\�s�����@����ȊO�ɂ��]���ɉ]���ʁE�E�E
�@���ꓙ�̊��R�̏]�i�₩��j�������ɂȂ�l�̏�ɗ�����
�@��ÁE�V���̉Ƃł͑�X�̉]���`����
�@�F�E���E�y�E��̎҂ƌ��𗘂��Ă͂Ȃ�ʁI������킹��ȁI�ł��\���`����
�@�����Ȃ薬���̂Ȃ�����N�@�Ȃ��m�g�j�̑�̓h���}�͉͈�p�V������l���Ƃ��Ď��グ�Ȃ��̂��H�E���ꂾ���̑�l�����@�������l���E����͖����ȗ��̐����Ƃ̎F���E���B�E�y���E���ɉ������Ă̂��ƁH�@���D�̐l���ɂ͊��R���̂�
�Q�P�@�͂Ȃ����E�����܂������E�߂�܂��ā@������������Ă킳�т����̏�ɍڂ��Ă�����l�E�@�Ƀc�[���Ƃ��ĊP���o�Ă��Ă��𖡂키�ǂ���ł́E��ɗn�����ĉ�����
�@�h�g�̏�ɂ킳�т��ڂ��ĐH����E��������l�@�ݖ��ɗn�����ċ��̖�����������Ɛ�ɓ`���āE���̑���W�������ڂ��Ȃ��ʼn�����
�@�]�˂̐̂͂킳�т͒l������̂œ��h�q�ł����E�J�X�o����T�[�r�X�͂킳�т̂Ƃ���
�@���Ή��̓V�Ղ�͎��Ԃ��o���Ă��p���b�Ƃ���悤�ɓƓ��̍H�v
�@���ꂮ��������Ƃ��܂��@��������������Ă����ЂƂ�����������̂��ƁE�T���̂�����Ɍp�������̂́@�₹�䖝�̐���̉ʂāE���܂�̂���Ɍ�����Ȃ��悤�ɁE�E�E
�Q�Q�@�₽�����i����j�ɊC�ۂ͊|���܂���@�|�����̂���ʂɂ��邻�Ə̂��Ă܂����Ȃ��Ȃ̂��H��͂��̖����ς�邩��ł��E������͐H�����Ƃ��ɏ�{�ɂЂ����ăX���[�Y�ɂ����̂ǂɗ���Ȃ�����ł�
�@���Βʂ͊C�ۂ̊|�����ĂȂ����肻�𒍕����܂��@���̂��Ƃ�Ȃ��ŋq�P�����グ�悤�Ƃ��āu����v���Ȃ��u����v�������j���[�̂Ȃ��G�Z���ΓX������܂�
�@�e���F�̂��Ɏ��M�̂Ȃ��X�ŁE��͂�s��������
�Q�R�@�V�Ղ�͂������̒��̂�ɓ˂�����ŋƂ̂��Ή�����@�V�Ղ�̖�����������ɂ����ꏏ�ɂ��`�H�@�����܂���
�@�V�Ղ�ɐZ����̎M��ʂɗp�ӂ���
�Q�S�@����n���̗L���z�e���̃��E���W
�@�A��̏W�c����ĂɃR�[�g���H�D��n�߂�@�N���[�N�ɗa���邱�Ƃ�m��Ȃ��@�z�R���������@�z�e���������ӂ��ׂ��@������͓ۂ�ŐH���Ă�̂Ɂ@���_�o�I�c�ɎҁI
�@���l�ɋ������E�����̏��オ��ō��z�c���o�T�b�E�o�U�b�Ɠ����u���@���l���H�����ɂ�������炸�E�c�Ɏ҂߁I
�Q�T�@����̎��E�₽�炨���V���܂��蓪�������鑽���̓��{�l�@�����V�ƈ���͕����ĂȂ������Ȃ炢�����ł��傤���H
�Q�U�@���Ǝ�����m�点��r�b�O�x���̃`���C���@�S������@�O���̕����s�v�V�Ɏv���@���{�̓��w�𗬂����Ȃ�H���l������
�Q�V�@�ςł͂Ȃ��s�ׁ@���h�����̂Ƃ��@��ɓn�����Ƃ���s�ׁ@������h����
�@�e�L���́u���������Ȃ����Ă�����Ȃ����@�������������Ȃ����Ă��肪�Ƃ������v�C���̐��E���r�W�l�X�E�ɂ��p����H�@���{�l���L�̃��X�y�N�g�����s��
�Q�W�@��Ђł������ł������ɉ���̌������Ȃ��̂Ƀg���u�����������悤�Ƃ���]�i�₩��j�@�������̂��݂��悤�Ɓ@�������~�߂��Ə�i�ɕE�]�����Ă��炢�����̂��H�@����Ǝ����͔�_���I�Ȏ��������ł��Ȃ��̂ɓ��̉��Ȃ��Ȃ�m��Ȃ��@���H���R�ɒ������Z�Z�̐l�E�E�E�Z�Z�Ƃ͂Ȃ��Ă����Ԃ̃��_�̒S���҂����̒��ɂ́@�������̉ʂĂ͓d�b�Ȃ�K�`�����@�ΖʂȂ�Nj������Ɛ^���ԂȊ�ł����Ȃ�Ȃ��R��@�]�~�\�������Ȃ��̂Ńp�j�b�N�ƂȂ�֏��̉Ύ��ɒ��P�ցE�E�E���P�@���P�N�\�̈�
�Q�X�@�Ăі�
�@�s�u�ō��Z�����u�w������v�ƌĂ�ł܂��@���Z���E���w���͐��k�Ɖ]���@���w���͎����@��w���̂݊w���ƌĂԁ@���ʂ��ĉ�����
�R�O�@�܂��s�u���Œm��Ȃ��i���l�j�l�����܂��@��������ƌĂԁ@���������Ăꂽ���Ƃ�����܂��@���ɕs�����@����������Ȃ炨���l����I�I�@���ł́u���������v�ƌĂ�Ă�����Ȃ����u��������v�ł͋���@�V���ł̌Ăі��́u�o�i���ˁj���܁v�u�Z�i���Ɂj���܁v�u���������܁v�u�����ꂳ�܁v�ԊX���Ƃł��傤���H�E�`�ł͂����g���Ă܂����E�_�炩���Ƃł�
�R�P�@���l�i�ЂƁj�̑��q�►�𑧎q����Ƃ�������Ƃ�����t�����Ȃ��l�����܂��@�]��ꂽ���l�́u�i�j���̐l�I���Ƃ̎g�����E��V��m��Ȃ��E�E�E�v�m�g�j�̃��M�����[�ԑg�̊��̔��Ƃ���@�����Ă���ƕs���ł�
�R�Q�@�V���قœI�Ă����
�i�C�j�u�K�b�c���v�͐H�ׂ�ӂ���ł𑽂͎��ۂނƂ��́u�O�b�c���v�ۂނƉ]��
�i���j�ǂ����̑��������₶���Ԃ̉^�]�ȂŃA�S���Z���o���]�T�̕\��Ő[�X�ƍ��߂Ă��邳�܂��u�Ƃ�����v�Ƃ��Ă���ƁE���������ɐZ���Ă���Ƃ��̂ЂƂƂ��\��E���Ƃ��]���Ȃ��ق̂ڂ̂Ƃ������̂��̃Y�o���������\�����V���̕���
�R�R�@���l�̔��X�@�v��ʍ߂���@���P����M����̂ł����˂��`�H�@��[���l���ĉ������@����ȏ�̍ߐl���o���Ȃ����Ɓ@���~�߂ɂȂ����Ȃ�@�`�H
��
�@�������͐V���s�ݏZ�@�����Ă�����̂Ɍ�ʑ̌n�@�ߔN��l���z�ɂ��A�߃o�X�Ȃ���̂��@���ނ��������邱�ƂɁ@�o�X�͓ۂ�͏��܂���@�d�ԂƈႢ�o�X�̃G�A�R���ł̓A���R�[���L���z�����܂���@���m���[����茚�ݔ�����ː��̗v��Ȃ��H�ʓd�ԁu�k�q�s�v���@������k�̊����ɉ��L�@��x�����^�s�@�e�w�Ԃ͒Z�����͂������̉w����̓R�~�o�X�Ł@�Ԏ��o�X�̏�q��}�C�J�[��������ɐU�蕪����
�@��̊X�̊������ɂ��@�ꓖ����I�s���������Ńo�X���S�̊ϔO���̂ā@���S���̒��ԗ����E�������o�J�����@�����炱���d�Ԃł�
�Q�@�s���̎��s�͖x�ߓ��H�ɂ������Ɓ@���a�R�X�N�V�����̂ɍ��킹�āE�E�E�V���Ɋό������������Ȃ����@���ł����Ȃ��̂Ɂ@�M�Z�삩��搅����H�v���Ȃ������@�����镨�ɐM�Z��E����������ā@����ȐV���̎��R���������ヌ�X�g�����E�~���c�Ƃ̒ʔN�ό��@�D�̍w����͍��E���E�s����̕⏕���@���㓇���ӂ̊������͑q�ɌQ���̓V��̍����𗘗p�����E���o���h�̈��H�X�@�����閜�㓇�̂a���O�����X�@���r���[�@�Ƃ肠�����̖�l���z�@��l�Ȃ��ʏa���z�肳�ꂽ�͂�
�R�@�{���E�Ò��̃V���b�^�[�X�@���ʂ�E��E���y�уL�b�`���J�[�̓��̉w�̘I�X�X�ʂ��n�o�@�o�X���Ă��炤�̂�����@�ɂ��킢������Ă��炤���炵�ďo�X���͖����I�@�J�ł���ł��A�[�P�[�h�E�����������������̂��I�@�ɂ��킢�̌��_�͎s�i�����j�ƍՂ肩��E�E�E�̂���]���Ă܂��@�܂��͐H�ׂ��̂����������߁@�A�N�Z�X�͘H�ʓd�Ԃł���E���ꂪ��{�ƂȂ�܂��@�Ղ�͐l����ԋ��������̉𗘗p���o�@���ǂ̑�D�̏�ɓ����������Ƃ炵�i�Ⴆ�ΐX�̂˂Ԃ��̂悤�Ɂj�X�ɂ͐�ʂɕ����яオ�点���f�B�Y�j�[�̂悤�ȑ�D��̃p���[�h��E���邢�͉̂�o���h��~���[�W�J�����X���͐�����Ȃ�������@���҂Ɨ��������肠�����M�C���ł̒��ɉ���Ղ�E������܂����Ɛ�ʂł����������E���C�Ɨ��C�̏��̉Ă̖�p
�@����̔M�C�Ɛ�ʂ̗��C�̂��߂������@�@���̍Ղ�ɕs�������Ⴅ�O�i���j�B�@��������܂��Ƃ���d����̃W�W�B�B�������͂�����@��ҒB���X�^�b�t�Ƃ��Ċ��E���̎w�~�܂�Ǝd��Ȃ�Ղ�͐��藧�@�i�b�Ɋ��ҁE�E�E�H�@�������i�b�͊Ԉ�����G���[�g�ӎ����̂āE�^�c��c�ł͘e���̋c���߁E�_�c���铙�̌�ʐ������ɓO���邱�Ɓ@���u�l�ԃo�J�ɂȂ�Ƃ��Ƀo�J�ɐ���Ȃ��قǃo�J�ł͂Ȃ��v���ꂪ�Ղ�@��҂�E�o�J�҂ɐ���E���āI
�S�@�֓��̗L������n�̒��������ِ����ց@�ꔑ�W���~�O��@�ܘ_�N���邵�̂������ɂ͂���ȃo�J�����g�R�ɂ͒ʏ�ł́E�E�E�[�H���a�H�Ȃ̂Ɉꕔ�t�����`�@�����ȊO�̏h�ł����l�@���B���t�����`���Ԃꂵ�Ă���̂��H���s�Ȃ̂��H����ȃo�J�ȁI�ד����I�a�H�����ƐS����@�a�H�̗����l�Ƃ��Ă̌ւ�͂Ȃ��̂��H����ȃg�R�ɂ͍s�������Ȃ��@����ł͂����Ȃ����ǁE�s�������Ƃ��E�E�E
�@�����͊m���ɘI�V���C�t���ō��E�J�ł����̂œ���܂���ł���
�T�@�V�������s�ɂ��邳�тꂽ����n�@�ꕔ���ق͊��ɔp�Ƃ��Ă���@�R�����Ă��̌������l����@�������Ĉ����͂Ȃ��E�Ȃ̂ɕ����Ƀg�C���͕t���ĂȂ��E����ȃg�R�C�w���s�̂Ƃ��ȗ��@�[�H�͍������Ĉ�C���̂̃J�j��A���@���̃J�j���ł���E�������ď������Ă݂ǂ�J�j�̐g���Ȃ��@�������Ȃ��R�b�v�̒��ɓ���J�j���R���ԁ@�t�߂͂��������Œ��H����H�������Ȃ��@��ނ��h�Ɉ˗��@�o�Ă����̂͊����\�o�����������ǂ�@������R���ԁ@�ǂ��ɂ������炵�����̂́E�E�E�Ȃ��@�̂Ȃ���̗��قR�����x���c��݂̂̓�����@������͓��������̂��@�]���i�悻�j�Ɣ�ׂ�w�͂�����Ȃ��E��̒��̊^�̓c�ɏh�@���ł��邱�Ƃ͕����t�g�C���ɉ��z���邱�Ƃ���
�U�@�⎺����̍����ؑ����Ă̘a�����فZ�Z���@�����ł͂Ȃ��̂Ń����o�[�ƂȂ��Ă܂��@�����̗[�H�̘a�H�̃t���R�[�X�i�ʏ�j�E�\�����Ȃ��E�ꐄ���@��͂���̊�{���O����������Ɓ@�A���z�c���q�ׂ�ۃz�R�����܂��U�炷�@���ɂ����̎ߌ������Ŗ�F�Ɍ������ĂP�T�O����ɂ���E�\�o������̒��œ��`�����N�u�킽�Z�v����@��x�H���Ă݂��Ȃ炢�����E�E�E
���̓�@���}��
�P�@���ނ��Ă����n�����@���⎆�}�̂̎���͏I������I����Ȃ��Ƃ͂���܂���I
�@�����������������炵�Ă����Ēl�グ�E���X�����������Ă������z�E�ޗ��ł��鎆�͒l�グ�ɁE�L�ҋy�ѐl����̋������グ�Ȃ��ẮE�E�E�n�����Ȃ�ł͂̎��g�݂��@�L�҂𑝂₳�Ȃ��Ă����������������L�����ڂ����܂��@�L�҂͈�ʂ̃��^�C����������Ώۂɂ��āi������T���f�[�����̕����j�ܘ_�Ⴂ���E���Z���E���w�����@�s���S�����L�҂ƂȂ�@�ߏ��E�m�荇���̏������L���������ƂȂ��Ęb����@���ꂪ���R�~�ƂȂ��čL����ǂݎ肪�����Ȃ蕔����������@������܂˂��Ă��̂܂܂ł͗]��ɂ��E�E�E�����܂ł����ɂ�����邠�����@�l�̌܂Ɖ]�킸�Ɂu����Ă݂Ȃ͂�v�Ɓ@������K�V������̉]�����߂���Ӂu���C�ł�ȁI�v
�Q�@�������̓r�[���i���Ƀh���t�g�j�E�E�B�X�L�[�i�N�㕨�łP�W�N�ȏ�S�R���ȏ�j�E���C���i������N�㕨�j�E���i���ƌ���������{���ł��E���[���e���v��������������œۂ݂܂��j�@�̂ʼn]���ꋉ���@������͓x�������������Œ����ɐ����|���Ǝv�������Ƃ��Ȃ��@���׃C�G���[�i����j�y���đu�₩�����Ď|���E��������ɓ���Ȃ��@���i�͊⎺�̎𑠂��璼�����Ă��炢�@������A���R�[���ɑ����ɂ͎��M������܂��ā@�E�B�X�L�[�͐̂���P�W�N���̂̃I�[���h�p�[�@�Ⴂ������ۂ�ł��āE����ȊO�́E�E�E
�@���C���͐ԃ��C���i�����ł͂Ȃ�������₵�āj�@�����Ɉ�Ԃ��������Ǝv�������C���̓r�W�l�X�N���X�œۂԃ��C���@���ꂩ��P�{�����~���郏�C������X��������ł����������̂Əo����Ƃɂ́@�[���ł��郏�C���ɉ�Ȃ��@�o������I�@�Ⴂ���o�����ɂ��E�������낤�ȃ@�`�_�����낤�Ȃ��`�@���̃G���W�W�C�I
�@���@����͊�]�ł����Ă���ȏ�̂��̂ł͂���܂���
�@���C���Ȃ炱�̐�o������邩���H
�R�@���i���{���j�ɖ߂��ā@������@������]�����悤�ɂ₽��x�������������E���̏�|�����Ȃ��@�������ƈꏏ�E�x����������Δ������̂��H�E�B�X�L�[�E���C���ƈꏏ�ő��������Q�����Ȃ���Ύ|���͏o�Ă��Ȃ�
�@�Ꮊ��C���̒��ɐQ�����g�̂�肩����N���V�b�N���y�����i�U���Łj�Ă̒ቷ�������@�E�B�X�L�[��C���̒����Z�p���Q�l�ɕ��Ȃ������Ȃ�H�@���ł��E�B�X�L�[�E���C���ł��i�]��ŗD���E�P�ʂłȂ甄���Ƃ͔F�����Â��悤�ł��@�ꎞ������Ŕ���Ă���������ȂɊÂ��͂���܂���@�|�݂̏�Ɂ@���R�~�E�]���E���킳�����E������̂ł�
�@�悭�䓖�n�̎�㎩�����o�ꂵ�܂��@�_���Ȃ�ł��˂��`�@����ϔO�E�䓖�n�ۛ��i�Ђ����j�������Ĉ�̒��̊^�i���킸�j�@���̂悤�ȕ��ɉ��������Ă��_���@���Ԃ̃��_�@��ōl���邱�Ƃ��ł��Ȃ���ÂȔ��f�H�E������c�ɂ��́@�䓖�n�ۛ��͂����i�����j�������E�Â�ł܂��Ă��Ă�����X�L���Ȃ�
�@���Ƃ��ĐV���̏��i����E�����ɏZ��ł���l�B���]���j�͍��͉͂̐���������̂���Ԏ|���@��Ԏ|���͎̂��̍ڂ����k�C���̉��̂�ł��@�������̒��̊^�@���̓y�n�̌����`����M���Ă���@�ꎞ���V���ł͏Ă��Ƃ艮�ł�������Ȃ��j�����Ȃ��������L�������Ɂ@���������]�_�Ə��j�E�ǂ̂悤�Ȑ���������Ȃ̂��H�@���x�ۂ�ł��|���Ǝv�������Ƃ́@��͌l��������Ɖ]������ǁE�E�E�˂��I�E�E�E
�S�@���Ȃ�
�@���Ȃ���̂́u�̂�v�i�{���j�Ɖ]���܂����@���鎞���̂̂���L�i���j�����ݍ��@����͑傫�Ȃ̂�łȂ��`�E���������ݍ��Ƃ���ł���ȏ���ݍ��߂Ȃ��@�L���ڂ𔒍����Ƃ����@�����T�Ō��Ă����l���u�A�b�I�L����V�����Ă���E�L����V�E���ȂE���Ȃ��ƂȂ����@����ɂ���܂��@�L���̂�����ݍ��ށE���ۂɌ��܂����@���͓����ʼnY�̉^�͉����@�����̎U�������Ă����Ƃ��됳�ɂ��̌��i�@���������ݍ����ł������Ă��E�������ɐV�����E��̓��m���[���@����̂悤�ɉL�̎�ɓV�R���Ȃ�������݂���V�����Ă����E���Ȃ�̎��Ԃ�v���l�ꔪ�ꂵ�Ă悤�₭���ݍ��ށ@����̔��͖{���������@�T���f�[�����̂������͊O�ɂ�邱�Ƃ��Ȃ��I��܂ł��t������
�@���̂��Ȃ��@�{�B�L���܂ܒV���̓X���@���Ȃ����̌ւ���̂ĂĂ���@�̐V���́Z���̂��₶����@�M�Z��ɐ�������V�R�̖��ɋߕt�Â��Ă����@�y�p�N�̓��͋x�݁@�����^���[�ɋ߂����Ȃ�������@���̐̓V�R���Ȃ������Ȃ��E�̂�Ȃ��Ƃ��͓X��߂�@�l�̗ǂ����₶����Őe�����͂Ȃ��������Ă��炤�@�F�����Ɍւ�������E�q�̐��b��������
�@�������Ⴄ�Ȃ��͎��̍�ɁE���Ă��ŁE���L������Ł@���̂��Ƃ��ȏd���@�����ӂ����~�@���Ή��Ƃ��Ȃ����͂��Ђ����̂ł��̓X�̊i���m���@���Ƃ��Ȃ����������Ԃ̎��̂܂݂͂��Ђ����̂ł��邱�Ƃ��
�T�@�����œˑR�ł����E��҂̓s���ɂ�薬���Ȃ����Ԃ̖��_��
�@�S���t�őŐ����ߏ��\���E�܂�X�R�A�����܂����k�i�₩��j�u�����܂ł��ď����������˂��`�@�₾�₾�E�E�E�Ȃ肽���Ȃ��˂��`�v
�U�@���̗���E
���̑O����u�炭���s�u�Ō���Ă���
�@���̒ʂ�@�v���̐��E�͌������Ɖ]����@�������Ȃ��̂͗���E�@��������邱�Ƃ��Ȃ��@�N�ł�����Ē�������ΐ^�ł��ɐ����
�@�v���Ɉ�ԕK�v�ȑf����K�v�Ƃ��Ȃ��@���_�͓��厎�����Ȃ����@���ꂪ�D��������E����ȉ��D���Œ�q���肷����Ƃ́u�Q���v�i���Ȗ����j�̉�@�����̎t���i�Ɖ]���Ȃ��N������̎t���j����Ԉ����@��M������������E�E�E�@���悻�l�����Ȃ�����ŐV��i�N�ł���������Ⴂ�j�̋ƊE�@�������̂͐̂Ȃ���̏]�퐧�x�����@���厎�����K�v�ł��@�P���Ă邵��ׂ�@�Q���ꂪ�����@�R���܂�̂Ȃ�����ׂ���@�S���N�������̂܂܁@�T�u�����n�i�V���v�̊ԐL�ь����@�U�_�W���F�[�i�v�l�j�⏗�`�������|���Ǝv���Ă���k�i�₩��j�@�V���m�}�l���ł��Ȃ��i���m�}�l�ł��Ȃ���|�l�łȂ��j�ʔ����̂Ȃ����Ƃ͑���ɂ���Ȃ��@�W�ŏd�v�̐^�ł������́u��H���ׁv����点��@���E�l�����ׂ̂��߂����ł��邩�ǂ����H�@���݂̐^�ł��ł��̔��������l�^�ɂł���͉̂ʂ����ĉ��l�H
�@���勖�͂����̑f������]�̂�
�@��ɑ�����������i�T��ځj�t���E���ڂɏo���@���ɂP�Q�R�S�T�ɋ������n���f�̂��锶�Ƃ���E��V�I�Ȃ��͓̂w�͂��Ă�����܂���E�������]�E�Ȃ��ꂽ�Ȃ�H�E�E�E�@����Ȃ��|�l�قǂ݂��߂Ȃ��̂͂���܂���@�Ȓ��ɂ��ӔC���@��ɒB���ĂĂ��Ȃ����̑��吨�̐^�ł������̂܂܂ɁE�E�E�@�Â���Ȃ̏ɖ߂��āE�H�D�i�H�j�ŗ���ʂ̒��������Ă邱�Ƃ����Ƃ���Ă邱�ƂɂȂ���@�z�[������ł͔��Ƃ͐������܂���@�̂̔��Ƃ͊�Ȃŗ���ȊO�̖ʔ����͂Ȃ����������E���җ������������݂�����ƌ���Ă������R�Ȑ��E
�@���Ƃ̊�ʂ����[�������E�u�[���ł͂Ȃ��^�̃t�@����n��グ��@����Ɣ��Ƃ��A��Ă���
������ŋ��ɂ���
�ȑO�m�g�j�s�u�ŗ��ꔶ���ŋ����̂ɂ��ĕ��f���ꂽ�@�������͂��Ȃ�����
�@����͗���̎��w�����x�������Ă����Ǝv��
�@�u�̕���{����Q�O�Q�R�E�P�O���P�U�A�P�V�A�P�W���@���F����v�̃|�X�^�[��ڂɂ���
�@���ꔶ���ŋ��ʼn���̂ɂ͓���Ǝv����@���̗v���͐F�X�Ƃ���܂�
�@�܂����͗���̃}�N���ɂ悭�o��������Ă��܂��@����͔��ɓ���O�ɕ���������̔��̋G�߂̌���ɘA��Ă����Ă���܂��@���̑�\��Ƃ��Čj�O�؏��́u�ŕl�v�Ɂu�����ڂ̂₵�狛���Ƃ����ƈꐡ�v�m�ԁ@�o��Ȃ炸�Ƃ��j���y�́u�D���v�ł́u�l���Z����l����������ł������܂��v���������̈�ƌ��Ł@���̂��܂ō~�葱�����~�J�E�������r�[��]���Đ^�Ă̂��Ԃ�Ƃ肷�������̏�i�������т܂�
�@���l�̗���͐�������̂ł͂Ȃ��@��ƌ��̕`�ʂŕ�����̓��̒��ɏu�ԁE�����o���܂߂���i����荞�܂��܂��@�ł����痎��̓��_���t�������E�Ïk����������ꂽ���ƂE�ς߂�ꂽ���Ƃ�I��Ŏg���̂ł��@�X�ɂ͂Ȃ���͏�ʁE��ʂœo��l���Ǝ��͂̏�i���H�v���ĕ�����̓��̒��̗��̋�Ԃɂ����ɃX�b�Ɠ����Ă������邩�@�܂��z�����G��`�����邩���@�@����𖡂��Ɖ]���Ĕ�����̘r�݂̂��ǂ���ł��@�̕��ꕑ��ɖ��l�̔����Ă��炢����
�@���̐V�������݁E��������}���܂�
�@���������z���ɉ̕���Ƃ��ĉ����闎�ꔶ�E�ŏ��́u�D���v���œK�ł�
�@��ʓ]���̏��Ȃ���������̔��Ł@��l�����̕�����҂��̂��̂́@�l�q�̗ǂ��₳�j�E�C�P�����@���̎q������������Ă����͂����Ȃ��@��������Ə��̎q�Ɉ͂܂�n�C���߂��n�C���߂��Ƃ����������������@��������u������@�I�I�i���H���j�v�Ɛ����|�����Ă������@���̎�l���̑�X�̎�U�߁u���O�Y�v�@���y���߂��ē��ɗ����Ċ����ɂȂ�����̏o����̑D�h�̓�K�ɖ��ɂȂ�@������\�Z�����i�Q�~�W�j�Ɖ]���܂��ā@����͋��ڒc�\�Y�ƌܑ�ڋe�ܘY�̖����R�T�A�U�N���ɐݒ�@�i�i���[�V�����j�u�l���Z����l����������ł������܂��v�Ŗ����J��
��ꖋ�E�Z�b�g�@�����E�D�h�̓�K�̕����@�����莞����������@��ʂɂ��߂��z�̋P�������ˁ@���̂܂����˂���K�̕����̓V��ɉf��@�����ɂ͐e���Ɠ��O�Y������������
��E�Z�b�g�@��̒��@�M�𑆂����̓��ӋC�Ȋ�E�E�E�ł�����ꓬ
��O���E�Z�b�g�@�����猩���낷�|���̂�������ɕK���ɑ����Ȃ�������グ�铿�ɂ����������|����u�����`���l���@�`���@���v���@�`���H�v
�u���̑O�����ˑ債�����Ƃ˂���ł����ˁ@�q����A�ꂽ���_�����샓���֗������Ƃ����Ⴂ�܂��āv
��l���@�M�̉���ɍ���M���炢�̋q�@���̌�������s�������傷��\���
��ܖ��@�M��U�����q�@����M���ď��߂͈��S���Ă������̂̏I���ɂ�
�@���̌܂̕\��E�����o�E��i�̊ς����E�G�ߊ�����k���Ƃ点�@�����ɂ������o���悤�ɂ��ĉ�����
�@���ɉ̕��ꂪ���ӂƂ���l����́@����ʼn]���l��@���l�Ɖ]��ꂽ�l�ł��[������o����ł�������ʉ߂��Ă�����������܂��@����͖��l�ƂȂ�Ɣ�����x���������Ă��܂��Ƃ���ȏ�̖������v�l��~���Ă��܂��̂��H�@�����₦��̂�����Ƃ��ēo��l���������𒅂Ă���Ƃ̋��ʓ_�������Ă���
�@�̕���@���̂|�������Ă����@����̐������ꂽ������荞�܂�邱�Ƃ��̕���Ɋ��҂��܂�
2023 10��16�� ��;��� �J��17;30
���邨�l�̂����ӂŊϗ������ĖႢ�܂��� ���߂̋яΒ� ���� �̖� �������� �g�̏�b�������k�� ��������������� ����Ƒ����Ō�����������ɂ��� �}���ł���ׂ�Ȃ��Ă��ǂ��̂� �V�엎��ɓ��� �V��ɂ��Ă͂��낢��Ȉӌ������� �ÓT����������ł͂Ȃ��� �V��������o��ƌÓT�ɂȂ� �������̂Ƃ��� �ÓT�ɂȂ肩�����V��͖��� ����͒����𒅂č��z�c�̏�Ō��܂� �����ɏZ�ނ��E�l�̔�����ɌF������̌�ʐ������̉����̂��B������ɏ��|���n�J�����^�K�̊ɂ^���Y�����ɓ��y���߂��Ċ����ɂȂ�����_�[�i ���y�̑f�ƂȂ����g�� ��[�쥎l�h�͍��͖��� �����̓}���V������a�l�̓l�N�^�C�p�̎В�����
�����čs�� �����čs�������Ȃ����͎ԂɐV���� ���Ԃ������ʂ�߂��錻��ł� ���Ԑ�̏���͑n��Ă����͂������Ɨ���鎞�Ɛ����l��������̑̎��Ɨ���čs������
���̂��� ����̑�ނ��̕���ʼn�������͂���܂���ł��� ���ҊO�� ! ���� �킴�Ƃ炵���^�C�~���O�Ō��ݗ���̕������� ���̕�����ʼn������Ă܂��e���r�Ŋς����� ����ł͌�邱�Ƃ̂Ȃ��V�[�������肰�Ȃ������Ă��܂�������������ł�
�����̗����]�������~�߂Ƃ��₷
�O��ɑ��� ����̃}�N���ɂ���
�����ߕv����ɉ]�킹��� �}�N���̖����Ă����̂� ��(��)�Ǝ^(����ׂ�̂���)�̖ʔ�������@�Ȃ��낤���� �����Ė{���̗���Ƃ����͂Ȃꂸ�Ă��Ƃ��낪�ʔ����悤�� �O�؏�(�O��ڌj�O�؏�)�� �ŕl �̖ʔ����͂��̎O�؏��Ɠ��̃}�N���ׂ̈� �ŕl �Ɖ]�����ꂻ�̂��̂����ɂ������낭�Ȃ�����@�Ȃ����ƍl���Ă���܂���� �}�N���o��ɖ��߂�ꂽ�G���������o���Ă��܂�
�����ڂ̂₵�狛(��)�������ƈꐡ
���c��Ŕ����̂Ƃꂽ�]�˂̍��̃}�N����U�� �����O�؏����炷��� �����̈�Ԏ|��������2���ł����� ���̍��ł͂Ȃ��炵�� �������ƑD�������̋q�S���Ă�� �� �ɂނĂ��ƥ��������̂��Ƌ����̘b�ɓ��� �����炪�}�N���̂������낳���Ƒ����܂��ȥ���ƈ��߂��� ������������CD(�Ă����ĕ������ɂ���)���x�����Ă� �����ĎO�؏��̂��E�l�����ׂ̂��߂� �����Ă��ăX�J�b�Ƒu�₩�R�J�R�[���ł͂Ȃ� ���������l�̂���ׂ� ���Ĕɐ� �����(�͂Ȃ���)�̓}�N���������Ɖ����Έ�l�O !
���Ɋ�Ȃ̂�����ɂ���
��ȂƉ]���Ƃ���� �z�[������ ��e���r���� �ƈႢ �N���ł邩�͂킩���Ă��Ă� �������邩�� �����ł���ׂ肾���܂ł킩��Ȃ� ����ɂ͉��Ғ��S�̍l���������� �N���������Ƃ��ꂽ ����Ƃ����̂Ƃ��̋C���Ŏ��R�̍ٗʂ��甶��I��ō����ɂ����饥��Ɩ�쐽�ꂳ��͌����Ă܂� ���������̊�Ȃł͂��ꂪ�ł��܂��� ��l�̎������Ԃ������Ƃ�Ȃ�����ł�
��(1967�N��)���{�q���Ōj�L�� (�̂�����)�t������X�������吨��߂Ă����Ƃ���������� �����͂��Ⴂ������H������܂��@�ƌ����Ă�������~�ł̏����Ǐ疖���Ǐ�̃n�i�������Ă����܂ł����ׂ��ɉ�����Ă���I���͢���C�����Ȃ����� !���Ⴂ�̥����Č��߂܂��� ��Ȃ̑��݉��l�͂����ɂ���̂ł� �����̐L���͂ǂ�ȃ}�N����U���Ă���̂��� ? �Ƃ̊y���݂��������Ă���܂� ���̐�ǂ�Ȕ��ɓ����Ă����̂��낤�Ƃ킭�킭�����ĥ�����ꂪ��� ! ��Ȃł������킦�Ȃ��Ȃɂ��� �O����ςȂ��ɂȂ����L���t���̍������ł��Ȃ����̂��� �����Ă͗���Ƃ̃t�@���N���u�𑝂₷���ƂɂȂ��� �����Ȃ�߂�܂��ăE�`�̑�w�����͎��Ƃ̃}�N���� �R�g���I������A�g�͑��V�����x�����ċۂ�Ȃ��� ! �ƒ������Ă���Ă���Ă܂��� �łȂ��� �n�i�������Ă��Ă���ׂ肪�t���K�q�����K�� ���q�w���̂��Ȃ���w�͎��R�x�����ς� �~�Ńl�^�̓n�i�V�Ƃ��Đ���オ�� ���̋��P���Ⴅ�O(��)�ɓ`���܂� �i�}�͂����܂���� �i�}�� �i�}�̓r�[�������ɂ��Ă����Ȃ�������l !
����܂� ������C���z���Ă���
����Ă��Ă� �����̋�C�͓����Ȃ�
�Α���� �o�X����ς�Z��� ���C�Ȑ��� ����ɗ���
�`�Z�̑����ɎQ��
���͂��̐��Ɉ��
���܂ŋ��Ă����̂� ���̐��͏�Ȃ炸 �₩�Ȉꎞ�オ�߂��ĥ���I��
���� �S��
���킢���c(����Ƃ�) ��������Ƃ��Ȃ��� ���V�s�͍����Ə��ʂ̉��ɂ��킢����� �Ƃ�Ƃ�ς�
�����ɎR�����܂����Ɉ������g���ŗ��荬�� �I����Ƃ�̑�p �|�����̂ł͂Ȃ��� ����Ⴛ���ł��傤
�悴���̎��v�ɂȂ�� �����l(���������) ���Ԃ̊ϔO�̖����l ������e���^ �҂�����鑊��̐l�̐g�ɂȂ���
���� �т̌U��
���ǂ� �m���g�C���Ŗ�Y�������V�����x�� �A�[�����킢���� ��ɃV�����x������т����� ��(���Ԃ�)��юU��
�c������(������)�͔����[(���q�|�ق���)�ł����ĘI�P��
���� �����ԑD��
�H�q(�������낤)�������낤�p�ȍ��~���ۂ��|�� �������낤�o���Ώo��C�Ōܔt�� �������낤 ����łȂ� �l�łȂ������Ő搶�˂��叫
�P���J��(��)�̃e�L��(�I�V��)�̑O�ɐw������ꂳ�� ��������@ ! � �e�L���������� ����͈̂��I���͑叫 ! �
����Ɩꂳ�� ����͓� � ���炸���̃e�L�� ����ł��叫�ɐ���� ! ������グ�� ���i�킯�˂����낤 �[ �[���珬���Ţ���̏�łͥ��???�
���ꏬ���̔ԑg�̓r���ł��� ��҂̓s���� �����Ȃ袐푈���Σ�Ɖ]����V�N�̎咣��ɐ�ւ��܂� ���ꂩ��̑I���L���Ґ���65�ˈȏオ �S�̂̎l�����߂܂� ���� �E�N���C�i�[���V�A� �p���X�`�i�[�C�X���G�� �����̐푈�ɕ\�����Ĉӌ���s�����N�������Ƃ̂Ȃ���X�c��̐��� ���̥̐�m���|���Ȃ���������ł��ӎv�������N�������䂪�y�ƌN�B
�������ߐ��̔M�a�Ɛl�͉]������Ȃ�Ƃł������ ������ �L�� ����̖��Ԑl��ʋs�E���܂������ŋN���Ă��� ���������{�̎�ҒB ���E�̎�ҒB���E���A��p���A�Ƃ��ăf�����n�߂Ă��� �̂̃x���A�̂悤�� ���� �q�A��̎�w�܂ł����Q������ ���̔���f���̂���{���v���o���ė~���� ���̃f���̍Œ�(���Ȃ�) �x���A�̃f��������˔@ ��������� ��Ȃׂ��`�����ā`��Ԃ��`�� �҂�ł��ꂽ�` �،͂�[���������� �₽���낤�� ���������`�ƕ҂���`�����Ɛ��R�Ƃ��� ��������̉̂̍������N����
�Λ�����@���� �w�����b�g�̃t�F�C�X�K�[�h���n�l���� �܂�@�� �𓊂��邾�����f���ł͂Ȃ�
�����ɋ���I�}�G ! ���Ȃ��� ! �Ȃ�Ɖ]���� ������������� ������� �푈��m��Ȃ��̂̎q�������楂���W�W�C�B ! ���� �e���Ȃ鏔�N ���̐��ɑ��݂����Ƃ��� ������ԍ炩�����ł͂Ȃ���
��ɍ炭�ԂƂ��� ���m�� ���������Ƃ� !
�V���v���q�R�[�� !
��푈���� ! ���^��
"�N���グ��I�(��������܂���)
��X�́`(�o�J�f�J�C���o����l�F! )���܂��`�ׂ����Ƃ́`������X�Ƃ����N����m�Ȃ�Ă��ƌ�������N���t���ė��˂��棢������ ! ���H�[���@�`�� !���� �����⥥��
���ł�����ӎ��������Ă��鏔�N��ł͂Ȃ��ꂡ���R�c�ɍ��� �f���ɎQ�����Ĉӎv�\�������悤 ���˂��Ăł����̎Q���͐��Ԃ��F�m���Ă����
����͗͂Ȃ� �f���̎Q���͖����Ȃ祥�
����B�Ȃ�@ �I���F�Ɖ]��(�I���l�l����)���F�`�������������̂�������!
��҂̓s���ɂ�� �����Ȃ����荞�݂�v���܂�
��ˉ̌��c
�Ђƌ��Ō����Ȃ��n(���イ�� ���イ�Ƃ�)���� ���������d�ł��� ���x�͉��ʂ̎҂ɑ��ĥ��
�T�^�I�ȓ�������
�䂪���� ��N�̉č��h�̍ŏI���̖� ��O��l�N���S�����璣������炤 ���� ���j�͎��g����
���Ⴊ�J���Ȃ� ���̂��Ƃ̓����ł����킹��c ���B �㋉���ɂȂ����Ƃ��ɂ� �����ĉ������ɂ͖\�͂�U���Ȃ� !
���� ��ˉ̌��c�̏��q�� ���̍l���Ɏ��炸 ���������̎��ŕ�����蒲���� ���肳�ꂽ�c���� ! �ꐶ����������邱�ƂɂȂ邾�낤
�����邱�Ƃ� ���̏�� �^�����q�ׂ邱�Ƃ����Ȃ����
�V�̛�� ���
������łł��� �o�J�ł͂��Ȃ� ����������� ����l������������������� �{���̊�ɂȂ�Ƃ��� �����ł��� ? ��Ƃ����������ɐq�˂�Ƣ�֏��ɓ������Ƃ��ł��悤����
�₽��q�� �ׂ��ׂ��Ɛ�����Ȃ���������ꂽ��b�̐��������� �؋�����̌|�l
��͂� �o�J�ł͋܂�Ȃ� ���I�ȓk(�₩��)�� ? ��Ԓ� IQ�l (�g��������)�����Ȃ�
��� (�I�V��)
���|���o�J����肨�ނ͎ア���݂͏�v�̗^���Y����Ɨׂ̊Ԓ�(���Ǝ�)�Ƃ̂��Ƃ�(��b)���͓V��(�Ă�Ƃ�)�����̒��X��݁[��V�����x�����Ă�������˂�����^���Y�����
!���F�Ƃ����Ă����₪�����ȃ@��Ԓ���T���z�����邩��������Ŕ��킸�ɍs�����܂��q���V�����x�����Č��������Ⴀ�����Ă��̂𥥥���������Ɖ]����˂��
�q��Ȃɂ����Ȃ镨�͂��邩��?������棢�������炱���ɏo���Ȃ����������ꂳ�l�O�ɏo������Ȃ����ģ
�i��S��
�L���ȐS���� ���l�Ƃ̑��Ɏ� ���̕�����S��������������Ȃ�Ă�� �����ۂ����ꂳ������ӂ̎R�͂��Ȃ����� ���ɂɍs���g�̂����딯�����ɂɂ����g�����Ƃ���� �w�������̓��̑� �ЂƑ����ɏ����Ă䂭 ���̖����������Ȃ� ����ȑz���ɂȂ����A�[�^ ������O�\���ȓ��ɂ�������ǂ݉����� �o�J�𑝂₵�Ă��҂��v���܂� �nj�O�\�����߂��܂��� ���������Ă��ċ������Ė���Ȃ��Ȃ�܂���В��`�������C�����ǂ����炵�Ă��`���肢�`������ł͔n����̗���CD(�V�[�f�[)���v���[���g���܂���В��H�`���肪�ƃH�`����Ȃ璼���ɂ����т��o�ăO�b�X���ƥ���`�����̂܂܉i���̖���ɥ����? ���� �킽���S���Ȃ�Ă��܂��� ���蓖�Ă��炦�Ȃ��Ȃ����� ���l�łȂ��Ȃ邩�� ? �?�?�
������̐S���� �i��h�̂����ꏗ�Y�� �Ԕ����̎G�Ђ�������� �����ɂȂ��Ă��炨���Ƃ��Ė����ƂȂ����͂Ȃ�
�S�������Ȃ������� �e���̉Ƃɍs�������Ȃ� �����ɂ͎Ⴅ�O7�`8�l�W�߂ăK���K���b�|�� ��������
�Q���������\�˂��h���h���ƒ@�� ��肪�������@!��w偂̎q���U�炷�悤�� �F�����f�� ���̈�l �l�l�M�̍f���X���ɔ�э��� �悤�₭�����������Ƃ����
�e������� �オ��˂��� �������ƣ�Ⴅ�O��ւ� �オ��˂���ł����������э��Ƃ� �ʃ@�Ԃ����Ĕ��������� ����������܂����ꂿ�������� �厖�ȕ��Ȃ����Ƃ����˂����� ��������҂ɋ���ł₷��C��ȃ����[��
��ꂽ�}�� �����Ă݂� ! ���ւ� ����ł���������o�J�����[ �֎q������᧣��֎q�D�`�ǂ���ť���f�P�G �G�w�w�b�ւ��ւ� �Â����݂Ă��̂� �����Ă������
�Z�� (����߂�)
�̗̂��� �f�J���V��(�f�J���g��J���g��V���E�y���n�E�G��)�������̓J���g���D���ł��ăx���O�\���͈ꕔ����������������Ă���̂��������ɂ͂Ȃ�̂��Ƃ��g�����g�?����l�w������N�\������ ������߂��̂��ƌ����� ! ���l�����ƒ��������[������˂��o�J�����[����[! ���l�͂��ꗚ(��)���Ă˂��̂� ? � ���l�����߂����Ă��
�̗��s�����L���b�`�R�s�[��X�J�b�Ƃ���₩ �R�J�R�[��
����̍��̏��q��g�C���̗������� ��X�J�b�� ����₩ �m�[�p���e�B�[� �킩�� ������ �[�� !
�ȑO����������g����̖����ɂ��č���x�������܂� NHK�g���ʼn]�� ��g���Ɖ]�����t�͑��݂��܂��� ��ȂőO���Ō�̍�����O�g��� �����蒼��̍������� �Ō�̍�����g���(��C)�ƌĂ� ���飂��炫�܂��� �g�����X�}�z�Ō�������ƥ����������������͐_�i����ł���? �������{�J���Ă܂� ���a49�N�� ���ꋦ��ҏW ��ÓT���ꣂɈ˂�� �g���͎����̎����Ă����(��C)�̂��Ƃ��w���܂� ����Ƃ̋����͈���x��ł�
��C�߂���� ���̔ӂ̋q��200�l�Ƃ��܂��� ���������Ȑ�����ȁ`���`���`��`�(������)�ƕ��������Ƃ��� �،�(���ꗿ)�̏オ�荂�̎������y���ɓ͂����܂�(���Ƃ̎O���͐Ȓ��̎�蕪) ��;�����莞�_�ŋq�����m�肵�܂� ������g��(��C)�������̉ƂɎ����ċA�� �����ČÐV����16�ɐ����̂� �\�Ɉ�������ɋq���������� ���̓��̋���������(�������ψ�ł͂Ȃ�)�ɕ�݂܂� ����������Ɖ]���܂� �����߂��߂��ɓn���܂� �ł����珬��ɂ���悤�� ����D ! ��Ȃ���(��)�������ĂȂ� ���ꂩ��݂�Ȃŋg���ɂł��J�荞��������˂��� ! ���ڃN���X�ł��� �����ł����炻��ȂɈА��ǂ��������Ȃ� ���Ȃ���(��)�������ĂȂ� ! �
�����(��)�B�A���ăV�����x������ �Q�邩����
������
��قȂǂͥ�������ł����ȣ�Ȃǂƕ��������ꂵ�����ƂΎg���ʼn��X�Ƃ͈�����悵�Ă����U��
�����̉ʂĂɏo����̐E�l(�e��)�̉Ƃɏ\�Z����(��K�ɖ��)�ƂȂ� �����̂����݂Ƃ� �\�Z�K�ł���Ȃ��� �����ǂ��Ȃ� ����̑O���߂�(�e��)�̃J�~�������悪����;��K�̂������낤���ɂ����₵�Ȃ� ��_�[�i ! ���܂ɂ� ������������ �s���ĉ������� ! ;����������t�����ĥ���s������ �����ɋA��� �߂��̕s�����������Ŕ������̃o���邩�� �ǂ�����鏊�Ȃ����Ȃ��`�� �������� ���O�֏� �����Ă��Ă��Ɖ������炵�₪�� �����͂Ă���? ������悤���˂�������B(������)�̘e�ɒu���� � ������˂���U�� ! � ��o�V�� ! ���b ! �����ɂ͗��܂�V�����x�������E�F !� ��A��Ƃ��܂��̃J�~���� ��U�� "�x�����Ⴀ��܂��� "�ƌ����Ȃ�U�����Ђ��������Đ�킸�Ƀg���g���g�[���Ɛ��ē�̒��ɓ��ꂽ ���̂��݂��������� ��Ǝv������ ? ���̂��߂����� ;�����̂��݂�������������悭�F��������Ƀ_�V�������Ă��Ď|���|���ƌ�����
�O�t�������肵������˂������?�
�X(���܂�)�Ύ�
�E�q�̗��璆 �X������o�� �����锒�n���Ă����� �Ɨ��̐g���Ă��������ƒm�邪 ���n�ɂ��Ă͒������Ƃ͂Ȃ����� �ꐡ�̒��ɂ��ܕ��̍� �l�Ԃ��n�������� �E�q�̐l��͂������֥���Ⴆ�Ƃ��Ă͕s�K��
���̔��̔������̂��肳��(��O�\�l)�q�͖������킢���� �����\���� ���o����Ȃ� ���ł͑ł��� �����l�Ԃł��Ȃ����ΘJ�ӗ~�[�� �������̒���̓T�^ �n�I�v�w���܂��₦�� ���l�̒U��(�\�܍� ��X�Ƃ͂����Ȃ����Ò������c�� �N������D����Ă���)�̏��삯���ނ��肳��������ʂꂳ���Ē������ƥ�������Ⴀ�������Ĕ��N���̊Ԉꏏ�ɋ����� ! �������邱�����Ȃ� �����Ȃ��� �ʂ�Ȃ��� ���ʂꂨ�킩�� �ʂ�Ȃ����b ! �����ǒU�߂̑O�ł����� ����ȗD�������� �ނ⑾�ۂŒT���Ă॥�� ��������� �ǂ����Ȃ� ! � ���������b���Q�� �˂��` �������B����
�^(���킸)����
�X�}�z�̉���Ƃ� ���[���قȂ� ���Ԃ̎n�܂�͌��\�̍� �̕���̑啔���̉���(����)�̘A���� ��H�y�̓��ɒ������݂Ȃ��� �e�����B���|�Ȃǂ����Ċy���Ƃ��납�痈����
�f�l�ŋ��̔��� ��k�ɂ�����������悤�� ������Y�ꂽ�̂ɋC�Â����� ���� �҂��g�����[��������� �����ł��ꂭ�炢�̃��m�������Ă�z�@���˂��� !��Z�B����b���ǂ��� �f�P�F���낤���� �E�D�� �f�P�F����h���낤���Ă��������� �������̏��̎q�Ɍ�������ڂ����܂킟���Ђ��ς��ᰂ��L�т������ ���@�����E�\���Ǝv����Ȃ��킦�Ă݂���ȣ��I�������` ��킦��D�`�I���F�̂��` ? �������`�������ċ�(����)�����ė����Ƃ܂��k�ނ�����ȃ��m���F�Ƃ��I�����܂��ȣ���k�������₢���˂� ���ꂾ�����h�ȃ��m�� �p�̒��X�̏����ɂ��ς��ɥ�����~�߂Ƃ� ! ����̂Ɣ�ׂ��� �����ƂȂ炠�`�
�O�l��
�̗̂��͏h�ꂩ��h��փe�N�e�N�ƕ����čs�� ����ł̓g�C�����d�ԓ���w���ɂ���̂ƈႢ ���̒����碒N���`���B�`�����Ă��Ă��ꂥ! � �������̃g�C�v�[�h���݂����ɏ��\�킸 ���̂��鏊�Ȃ炵�Ⴊ�ݍ��� �̂��̂ǂ��Ƃ͌�������L�т�Ƃ��`�S���킵����O�\���ȁ`��l�����ʂ��ƕӂ�L���� �L���� �S�J�̉ʂĂɓr���Ő�グ��c�v���̐Ȃ��� ���������[�̗����V���� �m���g�C���ł͍����Ă���ׂ� �X���̃g�C���ɂ������Ă���܂�
�I�������� �c�������͎��ŋz����� �V�����g�C���̐������Ȃ� �����V�����g�C�������邩��܂����� �����y�b�g�̋��ꏊ����� �t�c�[�Ԃ̕I�˂��̓n�l�オ��u���ꏊ�͂��邪�O���[���Ԃ̓n�l�オ��Ȃ� ���ɒu���ƐU�����`���X�g���X�� ���������Ă���ԏ��ɒ��ӂ��ꂽ �R��������� �l�ڂ̉w�O�̏Z�܂����� ���q�������w�܂ŎԂő��} �y�b�g�̏�Ԓ������ĂȂ��̂Ŏd���Ȃ��� ? �O��������Ɖ���Y�ꂸ �̗Ⴆ�ʂ�̉䂪�Ƃ̂����l ����������� �~�}�����̖T�ɗ����ĕt���Y���@���������Ă��� �����Ɨ�܂��Ă���Ă��� ���肪�Ƃ� !
������
������o�߂� ���̎|���� ���ˎ��炸�
���ۂ݂� ����������� ���������� ���ߎl�p�ł��Ƃ͂������������˂̖炸 ��˂̓Ŏ��炸�
����̖������ɍs���Ă݂���2������
�܂��O���ڂɖ߂肽��� �����݂�����������ɉ� ���Δ����͂���ł̂��������� ��� �[���̓����ɔ��� �����Ă��Ă������ ����~���Ȃ����楥����ǂ�����Ȃ��� ���������ɂ��邩�磢���Ȃ����������� �����ɂ��������ƐQ�Ă��܂���ł����̥�E�D���`�܂�Ȃ���� ���������Ă���S�Z�����Ă����Ȃ��Ƣ���̎����� �~�߂��ጙ����ۂ܂��Ă����ꂳ �܂�������ӂ��� �����Ȃ��
�c��̐��� ��
��X�c��̑�ꐢ�� �זv�̐��� ���̐��ɕʂ�������颃g�L����߂Â��� ������Ƃ����Ďq�⑷�� �e���F�̐����l�� ���̗������Ƃ��Ďc�����Ƃ͂���قLĵ����Ȃ� �����l����x�͂���킩������l���鎞�� �����Ȃ�̍l�����m�������͂����O�� ���������a�ƌ���� �w���S�̂��v�`�u��=�C���e���P���e���[�̗��Ƃ݂Ȃ�(�l��i�w��20%�O��)�����O�h�v�}���� ���Ȃ��Ƃ��ɓ��m�ւ̎v�z���w��ł����Ȃ� ���̂܂܂ł� ���̒��n��l�G�� ���ʘ_�łȂ� �唼�̃v�`�u���\���R�͊F�����v���Ă��� �f���Q���̓��@�͂ق��ɂ��������̂�? �O���R�I�v�������悤�ȃ��[���@�b�N�̃e���[�Y�Ɠ����� �����̒Ŗ��O��������{�̓x�g�i�����痣��Ă���̂Ŕ�Q�͋y�Ȃ���Ƃ̈��S�������l�ԥ���{���ǎҥ��w�Ǘ��ҥ���{�̌��͍\���̑̐��̖ڂ̒��ɕs���������o�����������̂� ? �����܂� ���̎�i�Ƃ��Č��͂̎��̋@�����ɐ𓊂� �����E��ꂽ��E��Ԃ�
�@�����̂悤�Ȃ���ȍ����������Ƃ͂Ȃ����� �l�ԂƂ��� ! �l�̐S�͎����͂��Ȃ� �U���I�s���̂��ƂɎc�������̂ͥ��S�̖� ���̗��Ԃ��Ƃ��ĊÂ��ƗD���������� �������鏗�Ɠ��� ����Ȑ���s�����q�⑷�͗����ł��Ȃ� �V���Ɍf�ڂ���颎��̗�������ɂ���o���K�i��o���Ă����G���[�g�Ƃ͈Ⴄ �������ނ�Ɣ�Ⴂ���̊זv���������Ă����̖��̂���l�� �����ă}�C�i�X�ɍ�p���Ă��Ȃ������Ƌ�����ׂ� �]�������̂͊������Ƃł���̐����̕s���̖ڂ�����ׂł����� �s���̗ǂ�������Ȃ̂��� ������ �זv���Ȃ������G���[�g���w���m���l�Ƃ͌ĂȂ� ��w�̓����ɖ��v�m���l��������ア�l�Ԃقǐl�̏�ɗ��������风���̎v�z�ɋÂ�ł܂�w�Ԏp���Ɍ����Ȃ�m�낤�Ƃ��Ȃ� �v���Ԃ�ɉ�����Ƃ��͕֏��̉Ύ�(���P�N�\)�ɂȂ��Ă��� �ω��ɑΉ��ł��Ȃ����IQ�l�̍����o�Ă����̂�? �l���ꂼ�ꥥ�����
4/8 �X�V
�c��̐���
�p�[�g 2
���肩��n�܂����S���� �����ł������Ȃ̂����玄����w�̗������w����Ɋ�t���̊z�ō��ۂ̌��܂��w �U���ɂ�����
���ꂪ���� �����}�̗����^�f�ƕς��Ȃ� �J��Ԃ����̂����̒� ����ȗ��s�s���𐳂����Ƃ��Đ��`�����������c��̐��� �� ���ɕ����l����ɂȂ�Ȃ̑��������点�� �g���͈ȉ��̌��t�ɚX������� 25�˂̂Ƃ������ɂȂ�Ȃ��l�ɂ͐S���Ȃ� 35�˂ɂȂ��Ă������̂܂܂̐l�ɂ͓����Ȃ� �`���[�`�� 20�˂܂łɎ��R��`�҂łȂ���Ώ�M������Ȃ� 40�˂ł��ێ��`�҂łȂ���Βm�\������Ȃ� �`���[�`��20�˂ŎЉ��`�҂łȂ���Ώ�M������Ȃ� 30�˂ł������Ȃ�Γ�������Ȃ����W���[�W��N���}���\�[
�c��̐���̓]���͎��R�̋A��
��㐶�܂�̊F���������������������x��̂��̊Î_���ς������������悤�ɂ��̍� ���`�Ȃ���킯�˂����̐��̒��������� �L���ē�����߂����敶��A�b�J ! �ʂɢ���̗�������ɍڂ�悤�ȃG���[�g�̎����b���Ⴀ��߂��������݂䂫�̉̂���n�܂�NHK�̃v���W�F�N�g X �Ɏ��グ��ꂽ�����̌��k���˂����� ������ �q���B�𐬐l������܂ň�ďグ�����Ƃ��B��̎�������Ƃ���ŗǂ��� �l�͐l �e���G�̓e���G �����������z�͂���Ηǂ� ������肷�邱�����˂��� �����肱�ꂩ���15�N�`20�N����܂��܂������� ���Ȃ��A�e�ɂ��Ă��d���͖����Ȃ邵���̖��ɗ����Ƃƌ����Ă॥��k�Ѓ{�����e�B�A������ ���ނ���~�߂Ă���[�l�l�̎ז��ɂ����ͥ�����̌�y���Z�̍�����̂����炢�̃W�����T�A�` ����̃{�����e�B�A�ł��������͓q�����̖������������ �����˂� �J�̉\�ł� �����̍���4��4��(���o���̓�)�ɑ���̂ŕ����I��ƌ����Ă���Ƃ� ���������������Ȃ�܂����� ���̎�ɂ܂œ��ꍞ�݂₪�� ���_�˂��`�Ȃ肽���Ȃ��˂��`�����炻�̓��� ? ���������Υ�����������̂� �ˑR ! �l�̐l�� ������˂����� !
Copyright Rakugoniigata Allrights
reserved.
�@
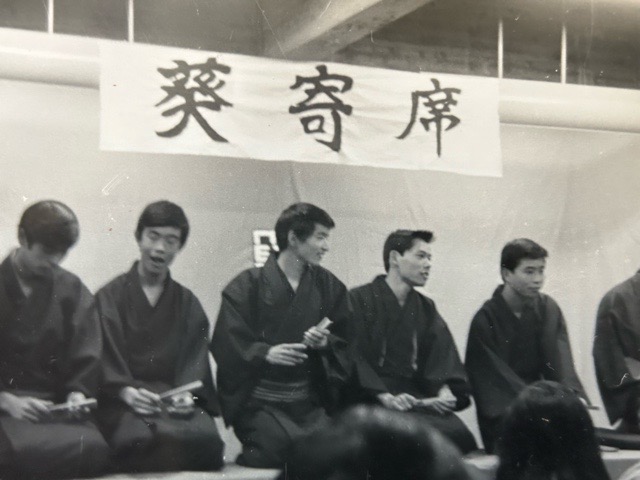
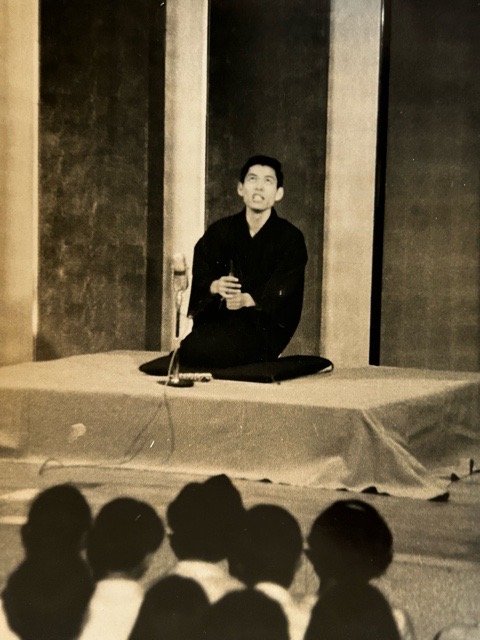
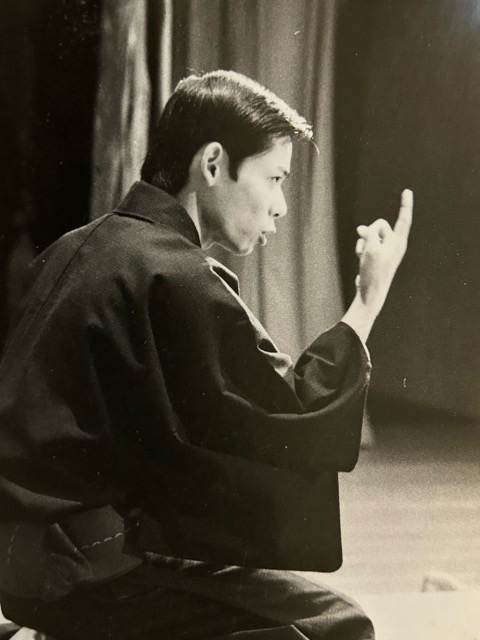
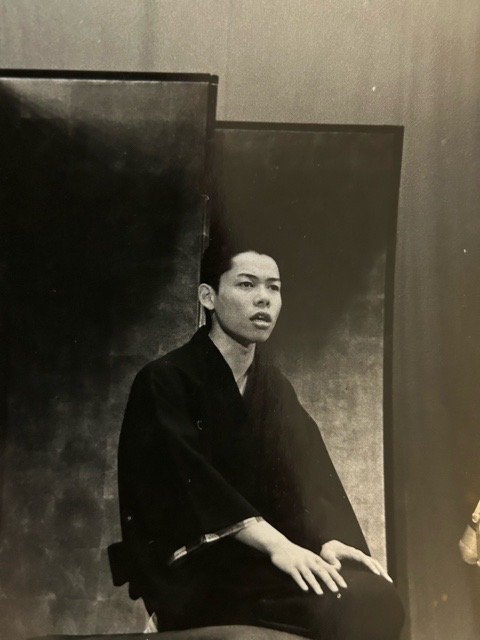
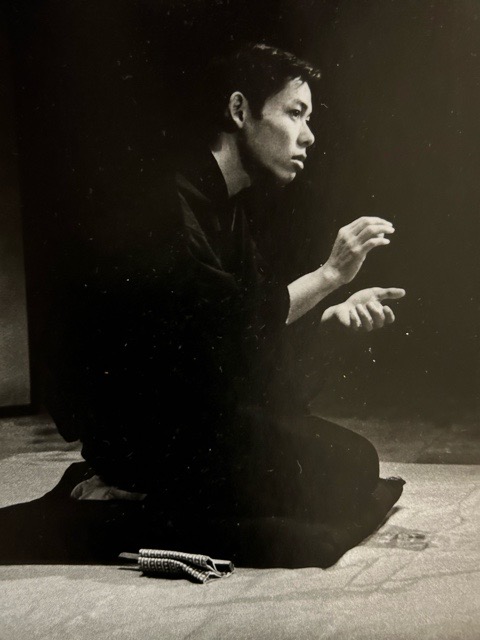

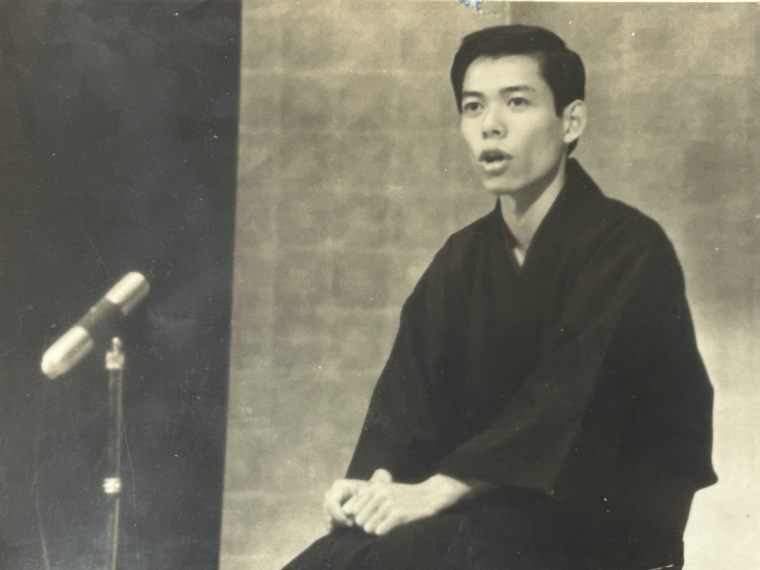
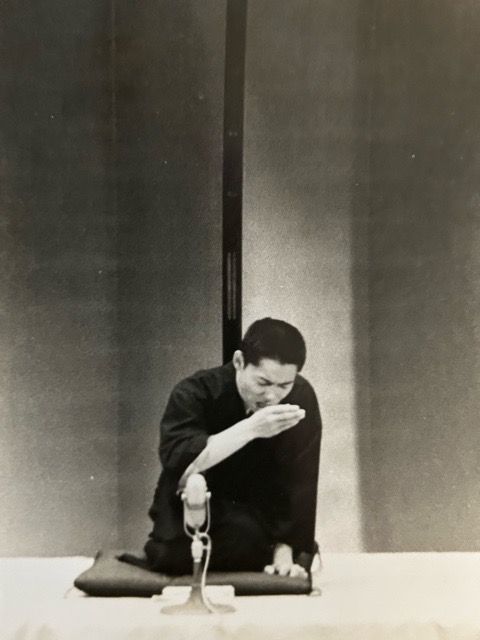


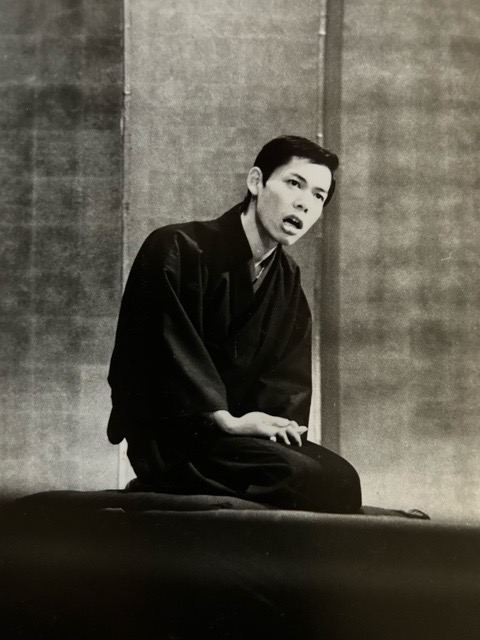
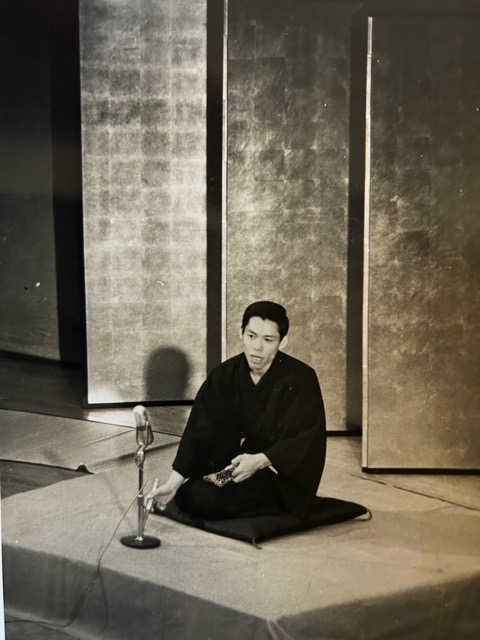

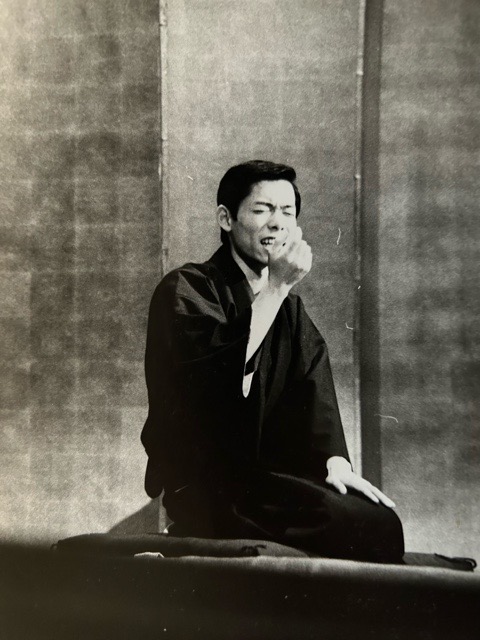



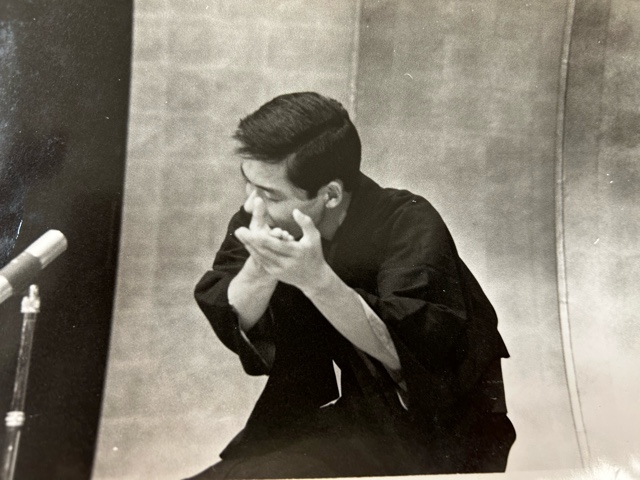
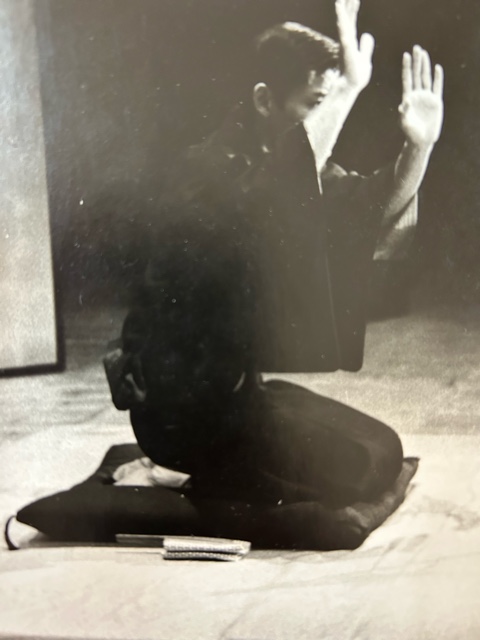
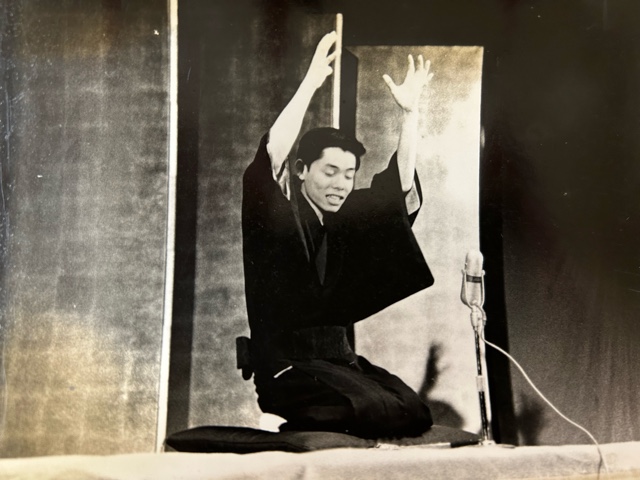
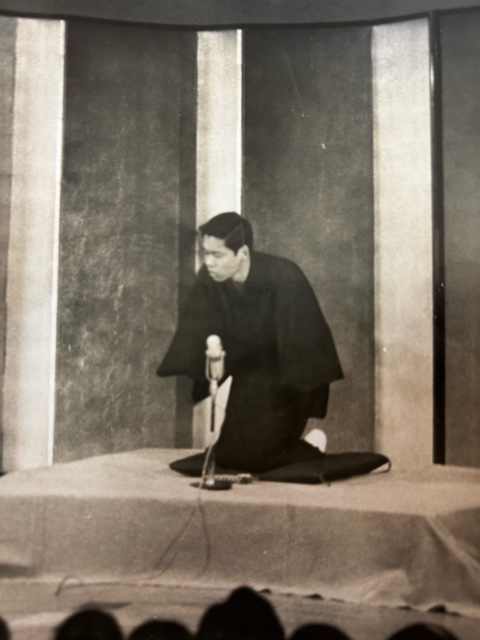
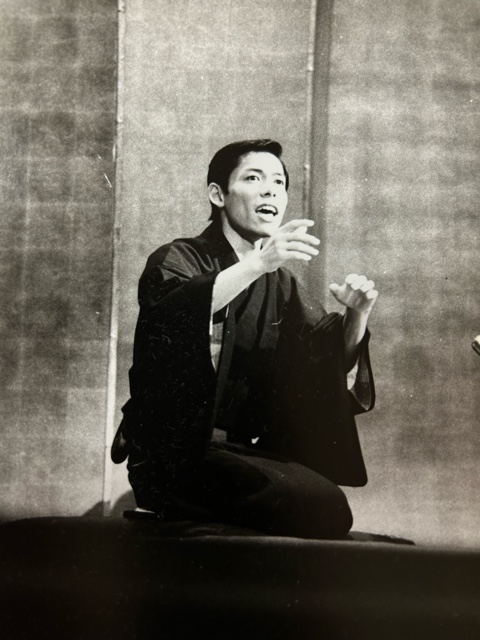
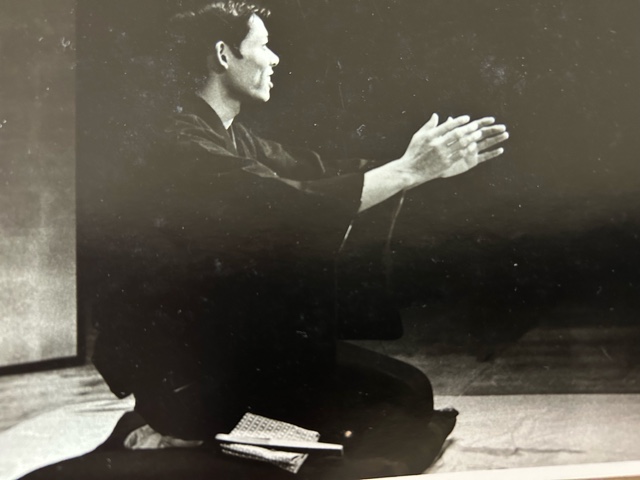
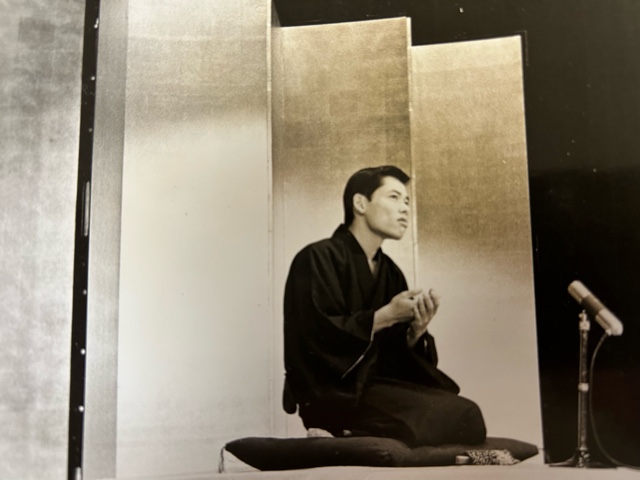
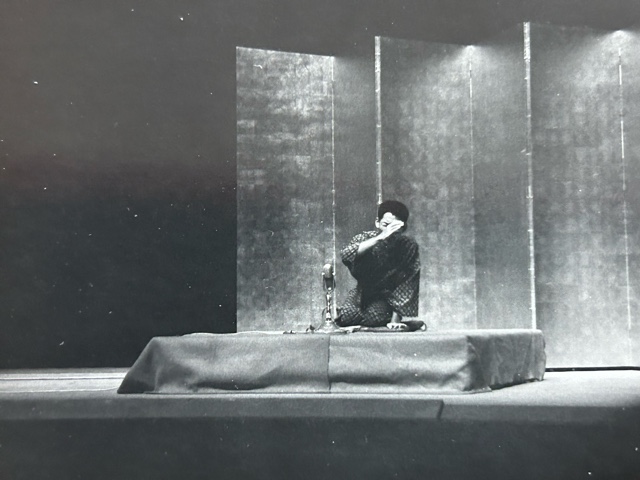

 �@�@�@�@
�@�@�@�@